PR

会社員を卒業してフリーランスになると、年金や老後の資金準備に不安を感じる方も多くいます。iDeCoや企業型DCを聞いたことがあっても、具体的な仕組みや活用方法がわからないケースはよくあります。この記事では、iDeCoと企業型DCの基礎知識や併用のメリット・デメリット、注意点をまとめました。
記事を読めば、自分に適した年金制度の選び方や、効果的な老後資金の準備方法がわかります。iDeCoと企業型DCを併用すると、節税効果を最大限に活用しながら、十分な老後資金を確保できます。ただし、併用には一定の条件があるため、自分の状況に合わせて慎重に検討しましょう。
» 資産形成に役立つiDeCoの基礎知識と注意点
iDeCo(確定拠出年金)と企業型DCの基礎知識
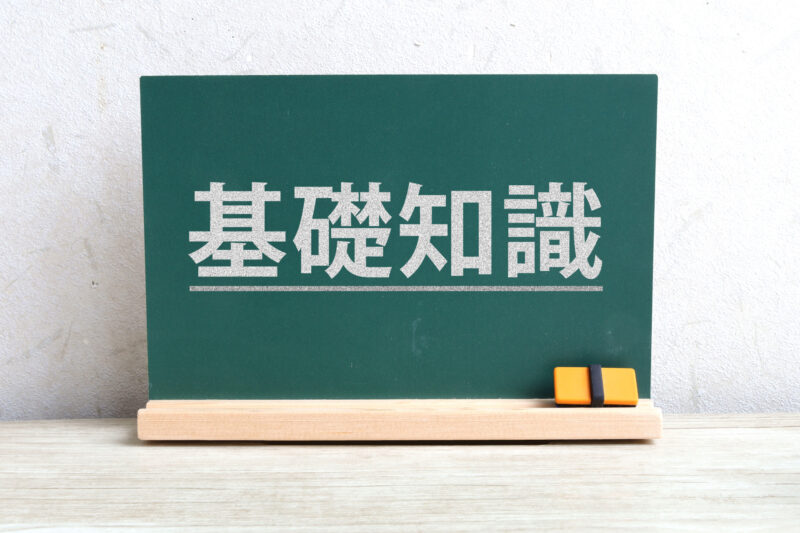
iDeCoと企業型DCは、老後の資産形成に役立つ確定拠出年金制度です。以下の項目について、それぞれ解説します。
- iDeCoとは私的年金制度の一つ
- 企業型DCとは会社が拠出する掛金が確定している企業年金制度
iDeCoとは私的年金制度の一つ
iDeCoは個人型確定拠出年金の略称であり、自分で掛金を払って運用する私的年金制度です。老後の資産形成に役立つ重要なツールです。iDeCoは税制優遇が受けられる点に特徴があります。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税です。受け取る際にも税制優遇があるため、長期的な資産形成に適しています。
ただし、原則として60歳まで引き出せない制限や毎月の掛金額に上限があるため、注意が必要です。2017年からは加入対象者が拡大され、より多くの人がiDeCoを利用できるようになりました。フリーランスにとっても、老後の資産形成を考えるうえで検討する価値のある制度です。
» iDeCoの上限額はいくら?職業別・加入条件別に解説!
企業型DCとは会社が拠出する掛金が確定している企業年金制度
企業型DCは、会社が従業員のために掛金を拠出する年金制度です。掛金額が事前に確定している点が特徴の一つとして挙げられます。企業型DCの仕組みは以下のとおりです。
- 従業員が運用方法を選択できる
- 運用結果で年金額が変動する
- 税制優遇措置がある
企業型DCは、iDeCoと同じく60歳まで原則として引き出せないので、老後資金の形成に役立ちます。転職時には企業年金の持ち運びが可能なため、長期的な資産形成に適しています。
» iDeCoと企業型DCを併用する方法を解説!
iDeCoと企業型DCを併用するメリット

iDeCoと企業型DCを併用するメリットは以下のとおりです。
- 節税効果が高い
- 老後資金を十分に確保できる
- 商品の選択肢が広がる
節税効果が高い
高い節税効果は、iDeCoと企業型DCを併用するメリットになります。掛金が全額所得控除の対象になるため、現役時代の所得税や住民税の軽減が可能です。特に高所得者ほど、節税効果は大きい傾向です。企業型DCの拠出金は給与所得控除の対象外になるため、追加の節税効果も期待できます。
社会保険料の負担が軽減される可能性もあり、結果として全体のコストを抑えられます。長期的には複利効果によって、資産形成上でも有利です。節税しながら老後の資金も準備できるため、メリットがあります。
» iDeCoの控除証明書とは?取得方法をわかりやすく解説!
» iDeCoの節税効果を最大限にするコツ
老後資金を十分に確保できる

iDeCoと企業型DCを併用すると、老後資金を十分に確保できる可能性が高まります。複数の年金制度を活用して収入源を多様化できるためです。以下の観点から、老後資金の確保が可能です。
- 長期的な運用による資産形成の可能性が高まる
- インフレに対するヘッジになる
- 運用次第で高い利回りが期待できる
- 公的年金を補完する私的年金として機能する
運用益が非課税で再投資される複利効果も得られるので、より効果的に資産を増やせる可能性があります。iDeCoと企業型DCを併用すると、老後の生活資金を増やす機会が広がります。退職金の上乗せ効果もあるため、より安定した老後生活を送るための資金確保が可能です。
» 退職後のiDeCoの運用方法と手続きの仕方、金融機関の選び方
商品の選択肢が広がる
iDeCoと企業型DCを併用すると、購入できる商品の選択肢が大きく広がり、より柔軟で効果的な資産運用が可能になります。iDeCoと企業型DCでは、それぞれ異なる商品が用意されているため、さまざまな投資先を検討できます。両制度の特徴を生かした商品選択もおすすめです。
iDeCoでは自由度の高い商品選択ができ、企業型DCでは運用コストの低い商品が多い特徴があります。それぞれを組み合わせると、コストと自由度のバランスの取れた運用が可能です。iDeCoと企業型DCを併用すると、より多くの選択肢の中から、経済状況に適した商品を選べます。
iDeCoと企業型DCを併用するデメリット

iDeCoと企業型DCの併用のデメリットは以下のとおりです。
- マッチング拠出と併用できない
- 手間と手数料がかかる
- 転職や退職時の手続きに手間がかかる
マッチング拠出と併用できない
マッチング拠出と企業型DCの併用ができない点は、デメリットの一つです。マッチング拠出は企業型DCでのみ利用可能な制度ですが、iDeCoと企業型DCを併用するとマッチング拠出は利用できません。逆に、マッチング拠出を利用している場合は、iDeCoに加入できないので注意が必要です。
企業型DCとiDeCoの併用を選択すると、マッチング拠出による節税効果を失います。マッチング拠出ができない影響は以下のとおりです。
- 自己負担分の拠出不可
- 企業からの上乗せ拠出不可
- 給与天引きによる積立不可
企業型DCとiDeCoを併用するかマッチング拠出を利用するかは、個人の状況によって異なります。自分にとって適している方法を選びましょう。
手間と手数料がかかる

iDeCoと企業型DCを併用すると、手間と手数料がかかります。両方の制度を管理する手間や手続きに時間と労力を要するためです。具体的に発生する手数料を以下にまとめました。
- iDeCoの口座管理手数料
- 企業型DCの手数料
- 運用商品ごとの手数料
資産が分散されるため、管理が複雑になる点もデメリットです。一方で手間と手数料は、長期的な運用によって得られる利益と比較すると、決して大きな負担ではありません。コストを考慮したうえで併用について検討しましょう。
» iDeCoの手数料の種類と節約方法
転職や退職時の手続きに手間がかかる
転職や退職時には、企業型DCやiDeCoに関連する手続きが必要になり、多くの時間と労力がかかります。必要な手続きは以下のとおりです。
- 企業型DCの資産移管手続き
- iDeCoへの移管または解約手続き
- 書類作成と提出
- 金融機関や年金事務所との連絡調整
手続きは退職金や失業保険の手続きと並行して行う必要があるため、煩雑になります。期限や締め切りがある点にも、注意してください。手続きには専門知識が必要であり、間違いがあると不利益を被る可能性があります。転職先の制度によっては、再度手続きが必要になる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
» 転職時のiDeCoはどうする?iDeCoのスムーズな管理方法
» iDeCo移管の落とし穴!スムーズな移行で資産を守る方法
iDeCoと企業型DCの併用が向いている人

iDeCoと企業型DCの併用は、以下の特徴を持つ人が向いています。
- 節税効果を最大限に活用したい人
- 老後資金をしっかり準備したい人
- 投資の選択肢を増やしたい人
節税効果を最大限に活用したい人
節税効果を最大限に活用したい人にとって、iDeCoと企業型DCの併用は魅力的な選択肢です。組み合わせると所得控除の範囲が広がり、税金負担の大幅な軽減が可能です。iDeCoの掛金全額が所得控除の対象になり、企業型DCの掛金も課税対象外になるため節税効果が期待できます。
制度の併用により、現在の所得税や住民税を抑えながら、将来の資産形成にも役立てられます。ただし、併用には一定の条件や上限があるので、適切な範囲で活用しましょう。
老後資金をしっかり準備したい人

iDeCoと企業型DCを併用すると、効果的に老後資金を確保できます。併用すると、以下の点で老後資金の準備に役立ちます。
- 税制優遇の活用
- 長期的な資産形成
- インフレリスクへの備え
- 公的年金の補完
- 分散投資の容易さ
定期的な積立を通じてコツコツと資産を増やすことができるため、ライフプランに合わせた資金計画を立てる際に効果的です。
投資の選択肢を増やしたい人
投資の選択肢を増やすことは、資産運用の幅を広げるうえで重要です。iDeCoと企業型DCを併用すると、さまざまな投資商品にアクセスできるようになります。投資の選択肢が増えるメリットは以下のとおりです。
- リスク分散の機会が増える
- 投資スタイルに合わせて選択できる
- 市場の変化に応じて資産配分を調整できる
- 新しい投資手法や商品を試す機会が得られる
さまざまなメリットにより、運用の知識や経験を広げられ、個人のニーズや目標に合わせたポートフォリオ構築も可能です。異なる運用機関のパフォーマンスを比較できる点もメリットになります。ただし、選択肢が増えすぎると判断が難しくなる可能性もあります。自分の知識や経験に合わせて、適切な投資商品を選びましょう。
» iDeCoの投資信託のラインナップ
iDeCoと企業型DCを併用する手順

iDeCoと企業型DCの併用には、いくつかの手順が必要です。具体的な手順を以下にまとめました。
- 併用可能か確認する
- 掛金を決める
- 金融機関を選ぶ
- 必要な書類を準備・提出する
- 運用商品を選択する
併用可能か確認する
iDeCoと企業型DCの併用を検討する際、併用が可能かどうかの確認は重要です。併用の可否は勤務先の企業型DC制度によって異なるので、人事部門に確認しましょう。企業型DCの規約や掛金額と拠出限度額、iDeCoの拠出限度額の確認が必要です。
情報をもとに、年収と年齢から拠出可能額を計算し、併用した場合の総拠出限度額を把握しましょう。併用する際の手続きも確認が必要です。確定申告の要否や退職・転職時の手続きなどを事前に確認すると、iDeCoと企業型DCの併用をスムーズに始められます。
ただし、制度や規則は変更される可能性があるため、定期的に最新情報を確認しましょう。
» 上手に活用!iDeCoの確定申告の手続き方法と税制メリット
掛金を決める

iDeCoと企業型DCを併用する際の掛金決定は重要です。適切な掛金設定により、将来の資金計画を効果的に立てられます。企業型DCの掛金額によってiDeCoの掛金上限が変わるため、注意が必要です。収入や生活費を考慮し、無理のない範囲で掛金を設定しましょう。具体的な掛金の決め方は以下のとおりです。
- 企業型DCとiDeCoの掛金配分
- 毎月の掛金と年単位の追加拠出
- 掛金の自動引き落とし設定
年単位で掛金を見直す計画を立てると、生活環境や収入の変化に合わせて柔軟に対応できます。
» iDeCoの掛金の上限や、金額の決め方のポイントを解説!
金融機関を選ぶ
金融機関の選択は、iDeCoと企業型DCを併用するうえで重要です。適切な金融機関を選ぶと、より効果的な資産運用ができます。金融機関を選ぶ際は、以下の点に注目しましょう。
- 手数料の比較
- 運用商品の種類
- オンライン手続きの可否
- 投資信託の売買手数料
- 運用実績と評判
- 資産運用のサポート体制
- 口座管理手数料
- 金融機関の信頼性と安定性
複数の金融機関を比較検討すると、自分に最適な選択ができます。ネットで情報を集めたり、実際に金融機関に足を運んで相談したりする方法もおすすめです。
必要な書類を準備・提出する

iDeCoと企業型DCを併用するには、適切な書類の準備と提出が重要です。必要な書類を以下にまとめました。
- 本人確認書類のコピー
- 基礎年金番号がわかる書類のコピー
- 企業型DC関連書類
- iDeCo関連書類
- 口座関連書類
- 運用指図書
書類は選んだ金融機関に提出する必要があります。書類の準備には時間がかかる場合があるため、余裕を持って行動しましょう。金融機関によっては追加で書類が求められるケースもあります。事前に確認し、漏れがないようにしてください。
書類の提出方法は金融機関によって異なるため、指定された方法で提出しましょう。適切な準備と提出を行うと、iDeCoと企業型DCの併用をスムーズに進められます。
運用商品を選択する
運用商品の選択は、iDeCoと企業型DCを併用するうえで重要です。運用商品を選ぶ際は、自分のリスク許容度の考慮が重要です。年齢や収入状況、投資経験などを踏まえて、どの程度のリスクを取れるかを見極めましょう。投資の際は分散投資がおすすめです。複数の商品に投資すると、リスクを軽減できます。
以下の商品の組み合わせがおすすめです。
- 国内株式
- 海外株式
- 国内債券
- 海外債券
短期的な市場の変動に一喜一憂せず、長期的な成長を目指しましょう。インデックスファンドは、低コストで分散投資ができるため、初心者にもおすすめです。ライフステージの変化や市場環境の変化に合わせて、適宜ポートフォリオを調整していきましょう。
iDeCoと企業型DCを併用するときの注意点

iDeCoと企業型DCを併用する際の注意点を以下で解説します。
- 併用可能な掛金の上限に注意する
- 長期視点で運用する
併用可能な掛金の上限に注意する
iDeCoと企業型DCを併用する際には、掛金の上限に注意が必要です。両制度の合計掛金額には上限が設けられているため、適切な管理が求められます。事業主掛金が月額2.75万円以上の場合、iDeCoへの拠出はできません。事業主掛金が月額1.55万円未満の場合、iDeCoの掛金上限は月額2万円です。
事業主掛金が月額1.55万円以上2.75万円未満の場合、iDeCoの掛金上限は月額1.2万円となります。年齢や加入している制度によっても掛金の上限が異なるので、自分の状況を確認しましょう。上限を超えて拠出してしまうと、税制優遇を受けられなくなる可能性があるため、注意が必要です。
長期視点で運用する
iDeCoと企業型DCを併用する際には、長期的な視点が重要です。定期的なリバランスによる資産配分の調整や、ライフステージに応じたリスク許容度も見直しましょう。積立投資によるドルコスト平均法の活用も効果的な方法の一つです。長期運用の最大のメリットは、複利効果の大きさです。
急激な引き出しは避け、計画的な資産形成を心がけましょう。長期的な視点を持ち、着実に運用を続けることが、iDeCoと企業型DCを併用する際の成功につながります。
まとめ

フリーランスにとって、iDeCoと企業型DCの併用は老後の資金準備と節税対策として効果的な選択肢です。組み合わせにより、節税効果を最大限に活用しつつ、十分な老後資金を確保できます。併用のメリットとして、高い節税効果や十分な老後資金の確保、投資先の選択肢の拡大が挙げられます。
一方で、手続きの手間や手数料、転職時の複雑さなどのデメリットもあるので注意が必要です。掛金の上限に注意し、長期的な視点で運用しましょう。