PR

- iDeCoにお金を預けて大丈夫なの?
- iDeCoはやめとけと言われて心配になってしまった
iDeCoの制度の仕組みがよくわからないことは、多くの人が悩む問題です。iDeCoには良い点もありますが、人によっては負担になる面もあります。この記事では、iDeCoをやめた方がいい理由やiDeCoのメリット、失敗しないためのポイントを紹介します。
iDeCoは効果的な資産運用の手段の1つです。記事を読めば、iDeCoの基本的な特徴から、注意すべき点や失敗しないためのコツがわかります。iDeCoの理解を深め、賢い資産運用を目指しましょう。
iDeCo(確定拠出年金)とは老後資金を貯めるための制度

iDeCoとは個人型確定拠出年金の略称で、公的年金にプラスして老後資金を自分で積み立てられる制度です。英語名は「Individual type Defined Contribution pension plan」 です。自分で選んだ金融商品(投資信託や定期預金など)で資産運用します。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
職業や加入状況により毎月の掛金の上限が異なるため、事前に確認が必要です。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税です。原則として60歳以降に年金または一時金として受け取り可能で、受け取り時には退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。
iDeCoはやめとけと言われる理由

iDeCoはやめとけと言われる理由は下記のとおりです。
- 原則60歳まで引き出せない
- 元本割れのリスクがある
- 手数料がかかる
- 自分で金融機関を選んで手続きする必要がある
- 掛金に職業別の上限がある
- 誰でも加入できるとは限らない
上記の理由は個々の状況や目的によって異なるため、すべての人に当てはまるわけではありません。
原則60歳まで引き出せない
iDeCoの掛金は老後資金の一環として位置づけられているため、原則として60歳まで引き出せません。途中解約や引き出しは基本的にできない仕組みです。例外として、障害状態になったり死亡したりした場合などには、60歳未満でも引き出しが許可される場合があります。病気や事故で障害状態になった場合などが該当します。
老後まで資金を動かせないため、短期的な資金需要に対応できず、資金の流動性が低いことがデメリットです。60歳以降でも受け取りには一定の条件があります。年金形式で受け取る場合や一時金でまとめて受け取る場合など、選択肢によって条件が異なるため注意が必要です。自身のライフプランに沿った資金運用が重要です。
元本割れのリスクがある

iDeCoの投資商品には、元本割れのリスクがあります。投資信託や株式などの運用商品は市場の変動に影響を受けやすく、資産の価値が下がる場合があります。経済状況や市況の変動により運用結果が悪化し、元本を下回る可能性があるためです。
リーマンショックのような大規模な経済危機が発生した場合、投資している資産の価値が大幅に下落する可能性があります。リスクを避けるためには、分散投資が有効です。複数の投資先に資産を分けることで、一部の損失を他の利益で補えます。投資には慎重な判断が求められるため、投資に対する理解と準備が必要です。
投資信託や株式などの運用商品は元本保証商品ではないため、リスクを十分に理解した上で運用しましょう。
» iDeCoが元本割れする原因と対処法
手数料がかかる
iDeCoの利用には下記の手数料がかかります。
- 口座開設時の初回手数料
- 毎月の運営管理手数料
- 給付時の手数料
- 資金運用の信託報酬手数料
- 運用商品の変更時の手数料
手数料は積み立てた資産の運用成果に影響を与えるため、事前の確認が重要です。
» iDeCoの手数料の種類と節約方法
自分で金融機関を選んで手続きする必要がある
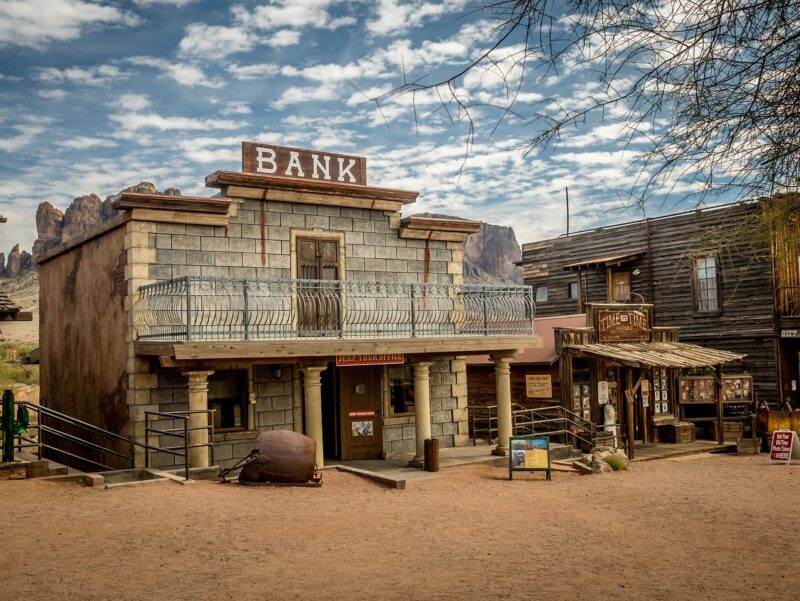
iDeCoは金融機関によって提供するサービスや手数料が異なるため、どの金融機関を利用するか選ぶ必要があります。適切な金融機関を選ぶことで手数料の負担を軽減し、iDeCoを最大限に活用できます。
手数料が低いがサポートが充実していない、手数料は高いが投資信託の選択肢が豊富など、金融機関によって特徴はさまざまです。金融機関の変更が面倒な場合もあるため、最初にしっかりと調査し、自分に合った金融機関を選びましょう。複雑な手続きの手間を避けるためにも、一度選んだ金融機関で長期的に続けるのがおすすめです。
掛金に職業別の上限がある
iDeCoの掛金には職業別の上限があります。職業に応じて月々の掛金が異なるため、事前に確認しましょう。職業別の上限額は下記のとおりです。
- 自営業者やフリーランス:68,000円
- 企業年金のない会社員:23,000円
- 企業年金がある会社員:12,000円
- 公務員:12,000円
- 専業主婦(夫):23,000円
誰でも加入できるとは限らない

国民年金保険料納付を免除されている人や、日本国内に住所を持たない非居住者はiDeCoに加入できません。日本の年金制度が、年金保険料を納められた国内居住者を対象としているためです。
» iDeCoは何歳から始められるかを解説
受け取り時に課税される場合がある
iDeCoの受け取り時には下記の控除が適用されます。
- 一時金として受け取る場合:退職所得控除
- 年金形式で受け取る場合:公的年金等控除
控除額を超える部分には所得税がかかります。受け取り方法によって異なる控除が適用されるため注意が必要です。適切な受け取り方法を選ばないと税負担が増える可能性があります。退職所得控除額を超える部分には税金がかかるため、一度に多額の金額を受け取ると所得税が高くなります。
年金形式で受け取る場合には、毎年の年金額が公的年金等控除の範囲内であれば税金はかかりません。しかし、他の退職金や年金と合算して課税対象額が増えることもあるので、非課税にならない場合もあります。
iDeCoのメリット

iDeCoには下記のメリットがあります。
- 積み立てた掛金が全額所得控除の対象になる
- 運用で得た利益が非課税になる
- 受取時に一定額まで非課税になる
iDeCoを利用することで節税効果が期待でき、将来の資産形成の役に立ちます。
積み立てた掛金が全額所得控除の対象になる
積み立てた掛金が全額所得控除の対象になり、所得税と住民税の負担を軽減することが可能です。控除額は年末調整や確定申告で申告する必要があります。年収が高い人ほど所得税率が高いため、高額の税の負担軽減が期待できます。
節税効果を最大限に活かすためには、掛金上限を理解し、範囲内で計画的に積み立てることが重要です。
運用で得た利益が非課税になる

iDeCoの運用で得た利益は非課税です。通常の投資信託や株式投資では、利益に対して20.315%の税金がかかりますが、iDeCoでは免除されます。
得た利益を全額再投資できるので、iDeCoは資産形成に最適です。通常の投資では100万円の利益に約20万円の税金がかかりますが、iDeCoでは税金が非課税となり利益を再投資に回せます。投資初心者にとっても、非課税枠があることで安心して運用できます。
受取時に一定額まで非課税になる
確定拠出年金の受取時には「退職所得控除」か「公的年金等控除」が適用されます。説明は以下のとおりです。
- 退職所得控除:一時金として受け取る場合に適用
- 公的年金等控除:年金形式で受け取る場合に適用
一時金と年金を組み合わせることもでき、両方の控除を利用して受け取り額を最大化できます。
iDeCoが向いている人・向いていない人

iDeCoが向いている人、向いていない人の特徴をまとめました。iDeCoを検討している人は参考にしてください。
iDeCoが向いている人
iDeCoが向いている人は下記のとおりです。
- 老後資金を計画的に準備したい人
- 所得税や住民税の節税を考えている人
- 長期的に投資できる余裕がある人
- 自分で投資先を選ぶことに興味がある人
- 安定した収入があり、毎月の掛金を無理なく拠出できる人
iDeCoは60歳まで引き出せないため、長期的な視点が必要です。20代や30代のうちから積み立てを開始することで、資産を着実に増やせます。iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の節税をしたい人におすすめです。特に高収入の人ほどメリットが大きいです。
iDeCoは自己責任で運用するため、自分で投資運用を学びたい意欲がある人は投資について学ぶ機会が増えます。株式や債券、投資信託など、さまざまな金融商品を選ぶことで投資スキルを向上できます。
» iDeCoの投資信託のラインナップ
定年まで安定した収入が見込める人にもおすすめです。安定した収入があることで、毎月の拠出継続が容易になり、長期間の積立で複利効果を増幅させます。
iDeCoが向いていない人
iDeCoが向いていない人は下記のとおりです。
- 60歳までに資金が必要になる可能性がある人
- 投資のリスクを取りたくない人
- 手数料を気にする人
- 自分で投資先を選ぶのが面倒な人
- 安定した収入がなく、毎月の掛金を拠出するのが難しい人
iDeCoは原則として60歳まで引き出せないため、急な資金需要がある人には不向きです。投資の運用に前向きでない人にもおすすめできません。iDeCoは市場の動向に左右されるため、元本割れのリスクが存在します。iDeCoは自分で金融機関を選び、手続きや運用を行う必要があるため、面倒だと感じる人には適しません。
収入が少なく所得控除の恩恵が少ない人は、iDeCoの節税効果を感じにくくなります。急な収入変動や失業のリスクが高い人も、安定的に掛金を支払うことが難しいため、iDeCoには向いていません。
iDeCoで失敗しないためのポイント
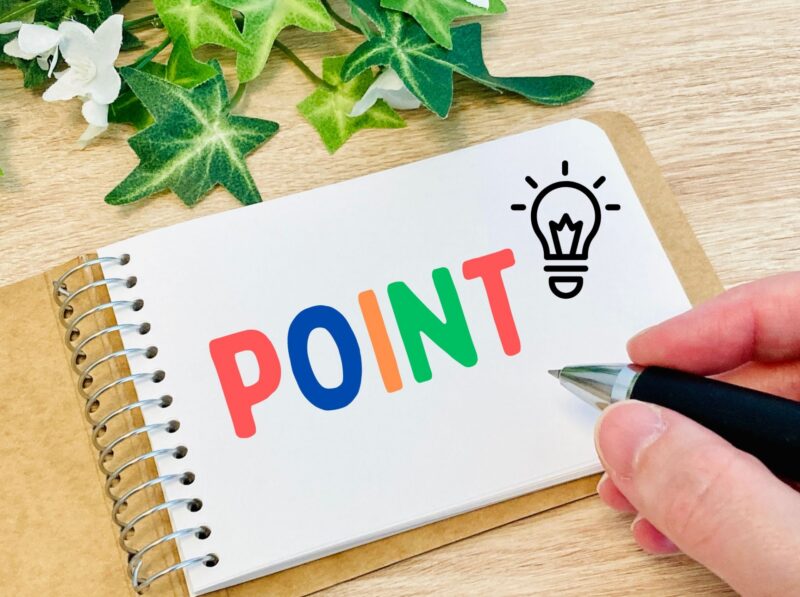
iDeCoを利用する際に失敗しないためのポイントは下記のとおりです。
- 60歳までに必要なお金は別で確保する
- 毎月の拠出額を無理のない範囲で設定する
- 手数料が低い金融機関を選ぶ
- 分散投資を行う
- 長期目線で運用する
上記のポイントを押さえれば、堅実な資産形成が期待できます。
60歳までに必要なお金は別で確保する
iDeCoは60歳まで引き出せないため、大きな出費があった場合には対応できません。大きな出費の例は以下のとおりです。
- 緊急用の資金
- 教育費
- 住宅ローンの返済
- 医療費
- 介護費
突然の収入減や予期せぬ支出に対応するため、生活費の3〜6か月分を緊急用の資金として確保するのがおすすめです。教育費や住宅ローンの返済などの大きな支出も計画的に準備しましょう。老後資金以外の目的で資金が必要な場合には、つみたてNISAや普通預金など、他の金融商品の利用をおすすめします。
医療費や介護費など、将来的に予測できない出費にも備えるために、医療保険や介護保険の検討も重要です。
毎月の拠出額を無理のない範囲で設定する

毎月の拠出額を無理のない範囲で設定することが重要です。自身の収入と支出の把握から始めます。生活費を見直し余裕資金を拠出に回すことで、家計のバランスを崩さず無理のない拠出額を設定できます。
定期的に拠出額を見直し、必要に応じて調整しましょう。家族と相談して将来のライフイベントを加味して、無理のない設定額を決めることが大切です。
手数料が低い金融機関を選ぶ
金融機関ごとに手数料が異なるため、手数料が低い金融機関を選ぶことで運用益を最大化できます。口座管理料や運用手数料が安価な金融機関を選ぶことで、コストを抑えた運用が可能です。ネット銀行やネット証券は一般的に手数料が低い傾向にあります。
手数料を比較する際には、金融機関の公式サイトや口コミ、比較サイトを活用しましょう。運用商品の種類やサポートの質の確認が重要です。
分散投資を行う

分散投資を行うことは、投資リスクを最小限に抑えるために重要です。リスクを分散することで、大きな損失を避けられます。分散投資方法は下記の4つです。
- 異なる資産クラスに投資する
- 国内外の市場に分散して投資する
- 異なる業種や企業に分散して投資する
- 投資タイミングを分散する
資産クラスとは、投資において類似した特性を持つ資産のグループを指し、株式や債券、不動産などがあります。異なる資産クラスに投資することで、特定の資産クラスが大幅に下落しても、他の資産クラスでカバー可能です。日本だけでなく海外の市場にも投資することで、地域ごとの経済リスクも分散できます。
特定の業種や企業に集中投資するのではなく、多様な業種や企業に分散投資することで、特定業種のリスクを回避できます。定期的な積立で投資のタイミングを分散すれば、市場の変動リスクを抑えることが可能です。
投資方法を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスを考慮したポートフォリオが作れます。長期的な視野で運用するための基本戦略として、分散投資は欠かせません。
長期目線で運用する
長期で積立投資をすることで、市場変動リスクを分散しドルコスト平均法の恩恵を受けられます。定期的に運用状況を見直すことは大切ですが、頻繁に変更するのは避けましょう。長期的な計画に基づいた資産運用を行うことで、安定した資産形成が期待できます。
まとめ

iDeCoは老後資金を計画的に積み立てたい人にとって有効な手段です。掛金が全額所得控除の対象となり、運用利益が非課税であるなど、多くのメリットがあります。
しかし、元本割れのリスクや60歳まで引き出せない点などのデメリットも理解しましょう。iDeCoを始める前にメリットとデメリットを十分に理解し、失敗しないためのポイントを押さえることが重要です。自分の生活スタイルや将来の資金計画に合わせた選択をすることで、安心して老後を迎えられます。