PR
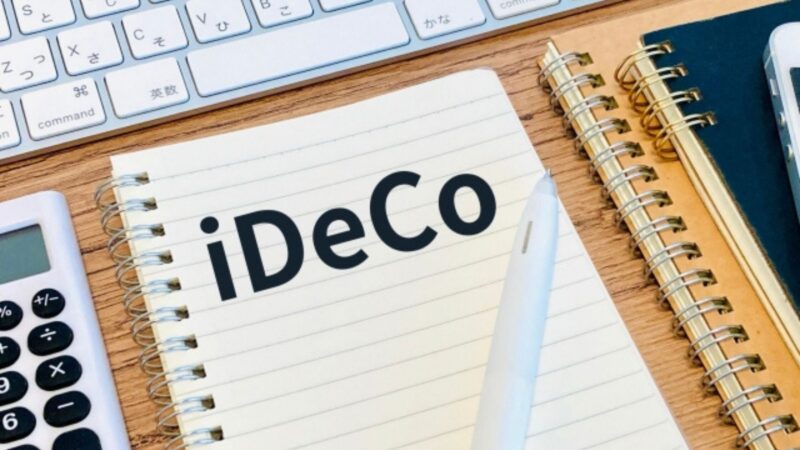
iDeCoに興味はあるけれど、よくわからないと感じている人は多いです。iDeCoは、老後の資産形成に役立つ制度です。この記事では、iDeCoの基本情報から加入資格、掛金の上限額、受取方法、申込み手続きの流れまでわかりやすく解説します。
記事を読めば、iDeCoの全体像が理解でき、加入を検討する際の判断材料になります。
iDeCoとは、老後資金を貯めながら節税にもなる制度

iDeCoは、公的年金で足りない老後資金を自分で積み立てて運用し、私的な年金を作る制度です。iDeCoの正式名称は「個人型確定拠出年金」です。iDeCoのメリット・デメリットについて、詳しく解説します。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
iDeCoのメリット
iDeCoの主なメリットは、以下の3つです。
- 節税効果が大きい
- 老後資金を計画的に積み立てられる
- 受取時にも税金の負担が軽くなる
節税効果が大きい
iDeCoの最大のメリットは、節税効果です。掛金の全額が所得控除の対象なので、所得税や住民税の税負担が軽減されます。運用益が非課税のため、利益が出ても税金がかからず、元本に加えて再投資に回せます。
» iDeCoの節税効果を最大限にするコツ
老後資金を計画的に積み立てられる
老後資金を計画的に積み立てられる点もメリットです。一度積み立てると、原則60歳まで引き出せない仕組みなので、確実に老後資金を蓄えられます。転職や退職といった職業の変化があっても、資産を持ち運んで積み立てを継続できます。運用商品の選択も自由で、投資スタイルや、リスク許容度に合わせた運用が可能です。
受取時にも税金の負担が軽くなる
受取時にも一定額まで非課税となるため、税負担が軽減されます。老後資金の準備をしながら、税金面でもメリットがある、お得な制度です。
» iDeCoは受け取り方が重要!最適な選び方を解説
iDeCoのデメリット
iDeCoの主なデメリットは、以下の3つです。
- 原則60歳まで引き出せない
- 各種手数料がかかる
- 掛金の変更は年に1回までと制限されている
原則60歳まで引き出せない
iDeCoは、原則60歳まで引き出せません。長期運用が前提のため、急に資金が必要になった場合に、柔軟に対応できない点がデメリットです。脱退一時金の受給条件が厳しいため、途中での脱退は難しいです。
各種手数料がかかる
口座管理手数料や運用商品の信託報酬など、各種手数料がかかる点に注意してください。費用が積み重なると、最終的に損をする可能性があります。資産運用には一定のリスクが伴うので、元本割れのリスクも考えられます。適切な運用商品を選ぶために、資産運用の知識も必要です。
» iDeCoの手数料の種類と節約方法
掛金の変更は年に1回までと制限されている
掛金の変更は年に1回までと制限されており、急な収入変動に対応しにくい点もデメリットです。途中で掛金を停止したり、減額したりする際にも制約があるため、資金繰りに困る可能性があります。制約を踏まえたうえで、計画的な資金管理を行いましょう。
自営業や副業をしている人が、iDeCoの税金控除を受けるには、確定申告が必要です。手続きに手間がかかるので、余裕を持って対応しましょう。
iDeCoの加入資格
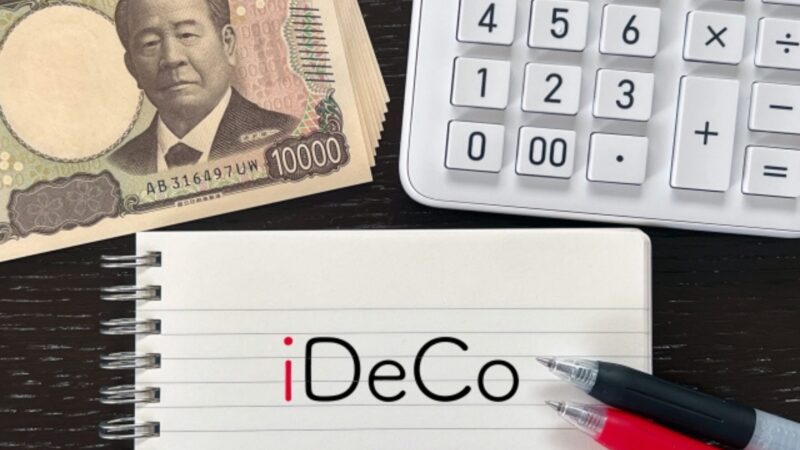
iDeCoは、日本国内に住む20~60歳未満の国民年金加入者なら、原則誰でも加入できます。iDeCoの加入資格について、ケースごとに解説します。
自営業者
自営業者の場合、国民年金の第1号被保険者の資格が必要です。個人事業主や自由業者、農業従事者などが該当します。企業年金がない自営業者にとって、iDeCoは老後資金を積み立てるための主要な手段です。加入には、証明書類の提出が必要です。
会社員

会社員の場合、国民年金の第2号被保険者の資格が必要です。企業年金がない企業に勤める正社員や、企業年金があってもiDeCoに加入できる企業に勤める正社員が対象となります。会社員がiDeCoに加入するためには、勤務先の証明書が必要です。掛金は給与から天引きされるため、手続きの手間も、支払忘れの心配もありません。
転職時には手続きが必要ですが、離職期間中も個人で掛金を払って継続できます。
» 会社員がiDeCoに入るメリットと年代別の節税効果を解説
公務員
公務員も、国民年金の第2号被保険者の資格が必要です。公務員や共済組合に加入している人が対象です。
専業主婦(主夫)
専業主婦(主夫)の場合、国民年金の第3号被保険者の資格が必要です。配偶者が厚生年金に加入している場合の配偶者が該当します。加入手続きは比較的簡単で、金融機関から申し込めます。
iDeCoの加入資格がない人

iDeCoに加入できない人もいるので、注意しましょう。iDeCoの加入資格がない人は、以下のとおりです。
- 企業型年金に加入している企業に勤めている場合、一部制限あり
- 公務員で共済年金に加入している場合、一部制限あり
- 20歳未満の人
- 60歳以上の人
- 日本国内に住所を持たない海外在住者
- 確定拠出年金法で定める加入者資格を満たさない場合
詳しい条件を知りたい場合は、金融機関や専門家に確認しましょう。
iDeCoの掛金上限額

iDeCoの掛金上限額は、職業によって異なります。生活環境や収入源によって、適切な範囲で積み立てができるように考慮されているためです。具体的な掛金金額を知ると、自分に合った積み立て計画が立てやすくなります。
自営業者
自営業者の掛金上限額は、月額68,000円です。公的年金が少ないため、老後資金を積極的に準備できるように、上限が大きく設定されています。
会社員
会社員の場合は企業年金の有無により、月額12,000~23,000円までの範囲です。企業年金がある場合は、掛金上限が低く設定されています。
公務員

公務員の掛金上限額は、月額12,000円です。一般的に安定した年金制度に加入しているため、追加の積立額が低めに設定されています。
専業主婦(主夫)
専業主婦(主夫)の場合、月額23,000円が上限です。家庭内の経済的な役割に応じた、適切な資産形成ができるように配慮されています。
iDeCoの受取方法

iDeCoの受取方法には、以下の3つの選択肢があります。税制面でのメリット・デメリットが異なるため、事前にシミュレーションしましょう。
- 一時金として一括で受け取る方法
- 年金形式で定期的に受け取る方法
- 一時金と年金を組み合わせて受け取る方法
受取開始年齢は、60~75歳まで選択可能です。受取の申請手続きは、金融機関で行います。
一時金として一括で受け取る方法
一時金として一括で受け取る方法は、まとまった資金が必要な場合におすすめです。住宅購入や旅行など、大きな支出に対応できます。退職所得控除が適用されるため、一定金額まで所得税が非課税になります。企業からもらう退職金の控除額と、計算方法は同じです。
| iDeCoでの掛金の支払年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×掛金の支払年数 ※80万円に満たない場合は80万円とする |
| 20年以上 | 800万円+70万円×(掛金の支払年数-20年) |
退職所得の金額=(iDeCo+退職金-退職所得控除額)×1/2だけに、課税される仕組みです。iDeCoの加入年数(掛金の支払年数)と勤続年数は、長い方で計算します。受取額は、加入期間や掛金額によって異なり、加入期間が長ければ長いほど増えます。計画的に受取タイミングを選ぶと、税負担を軽減できます。
年金形式で定期的に受け取る方法

年金形式で定期的に受け取る方法は、毎月安定した収入が得られる点がメリットです。生活費や日常の支出をカバーするための収入源となり、老後の生活を安心して送れます。公的年金等控除が適用されるため、税負担が軽減されます。
一時金と年金を組み合わせて受け取る方法
一時金と年金を組み合わせて受け取ることも可能です。ライフスタイルや経済状況に合わせて、割合を自由に設定でき、両方の税制上のメリットが受けられます。受取時の税金が分散されるため、税負担を軽減できる点もメリットです。
iDeCoの申込み手続きの流れ

iDeCoの申込み手続きの流れは、以下の3ステップです。
- 書類を取り寄せる
- 書類に記入する
- 書類を提出する
書類を取り寄せる
必要な書類を取り寄せましょう。iDeCo公式サイトや証券会社、金融機関のWebサイトから、簡単に取り寄せられます。住信SBIネット銀行や、楽天証券などが対応しています。取り寄せには、個人情報の入力が必要です。入力が完了すると、書類は通常1週間程度で郵送されます。郵送費用は無料です。
書類をダウンロードできる金融機関を選べば、迅速に手続きを進められます。
» iDeCo(個人型確定拠出年金)を始めるための必要書類を解説
書類に記入する

書類が届いたら、正確に記入しましょう。基本情報として氏名や住所、生年月日などを記入します。加入者区分では、自営業や会社員、公務員、専業主婦などの職業区分を選びましょう。掛金額は自分で決められるため、無理のない範囲で設定してください。
掛金の引き落とし口座となる、銀行口座の情報を正確に記入しましょう。受取方法は、年金や一時金、一時金+年金の中から選びます。納付方法も月払い、年払いなどから選択します。本人確認書類を添付し、署名して捺印しましょう。
書類を提出する
書類の提出は、重要なステップです。提出書類に不備があると、申込みが受理されないためです。間違いや記入漏れがないかを注意深く確認してください。運転免許証やパスポートなど、必要な本人確認書類を添付します。
書類がそろったら、郵送またはオンラインで提出しましょう。提出先の金融機関の指示に従って、郵送先の住所やオンライン提出の手順を確認しておくと、スムーズに進みます。提出後の受付確認を行うと、手続きが完了したことを確認できます。
iDeCoの加入資格に関するよくある質問

iDeCoに加入できるかわからない人は多いです。以下で、iDeCoに加入できる条件や、特定の状況下での加入可否など、よくある質問を取り上げてわかりやすく回答します。
- iDeCoに加入できる年齢は何歳から何歳までですか?
- 海外に住んでいる日本人もiDeCoに加入できますか?
- すでに他の年金制度に加入している場合でもiDeCoに加入できますか?
- iDeCoの掛金は途中で変更できますか?
iDeCoに加入できる年齢は何歳から何歳までですか?
iDeCoの加入資格には、年齢制限が設けられています。加入できるのは、20~65歳未満の国民年金加入者です。加入申込み時に20歳以上であることが条件で、65歳の誕生日の翌月からは新規の加入が認められません。すでに加入している場合は、継続が可能です。
自営業者やフリーランスなど第1号被保険者は、70歳未満まで加入を継続できます。国民年金だけでは年金額が少ないため、長期間にわたって年金を増やせるようにするためです。職業などによって、加入条件や掛金の上限額が異なるため、iDeCoのどの加入区分に該当するかを確認しましょう。
海外に住んでいる日本人もiDeCoに加入できますか?

海外に住んでいる日本人は、基本的にiDeCoに加入できません。iDeCoの加入条件は、日本国内在住だからです。海外在住で、日本国内に収入がある場合でも、加入できません。 日本国内に住所を持ち、海外出張や一時的な滞在なら、加入できる場合があります。
長期的に海外に住む場合は、iDeCo以外の個人年金や貯蓄方法を検討しましょう。
すでに他の年金制度に加入している場合でもiDeCoに加入できますか?
すでに他の公的年金制度に加入している場合でも、iDeCoに加入できます。公務員や私立学校の教員、国民健康保険の被保険者など、さまざまな職業の人がiDeCoへの加入が可能です。加入している年金制度によって、iDeCoへの加入条件や手続きが異なる場合があるので、事前に確認しましょう。
企業年金や厚生年金に加入していると、掛金の上限が変わる場合がある点に注意してください。
iDeCoの掛金は途中で変更できますか?
iDeCoの掛金は、途中で変更が可能です。年1回、設定された変更月に変更でき、変更した掛金額は翌月から適用されます。設定された最低掛金と、最高掛金の範囲内で行ってください。掛金の増減により、将来受け取る年金額に影響を与えるため、慎重に決めましょう。
まとめ

iDeCoは「個人型確定拠出型年金」という私的年金制度で、掛金や運用先、運用方法を決めて、長期運用が可能です。運用リスクがあったり、手数料がかかったり、60歳まで引き出せないことがデメリットです。
自営業者や会社員、公務員、専業主婦(主夫)が対象で、掛金の上限額は職業によって異なります。受取方法は、一時金、年金、一時金+年金の3つです。一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」といった税制優遇が受けられます。
iDeCoを活用することで、老後資金の形成に向けた計画的な資金運用が可能です。