PR

年金制度に不満があり、老後資金に悩む会社員は多いです。iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用すれば、税制優遇を受けながら老後資金を自分で積み立てられます。老後資金問題の解決に、iDeCoは有効です。
この記事では、iDeCoの加入条件や始め方、メリット・デメリット、年代別の節税効果について詳しく解説します。この記事を読むことで、自分に合った老後資金の準備方法を知り、将来に備えましょう。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
会社員がiDeCoに加入するメリット

会社員がiDeCoに加入するメリットは多数あります。iDeCoのメリットは以下のとおりです。
- 掛金が全額所得控除となる
- 会社以外の年金を確保できる
- 転職しても保有資産を移換できる
iDeCoに加入することで、税制上のメリットを受けながら、将来の年金への安心感を高められます。
掛金が全額所得控除となる
iDeCoの掛金は、全額が所得控除の対象になります。iDeCoの掛金が年間で12万円の場合、節税効果は約1.8万円です。掛金が全額所得控除になることで、毎年の節税効果を得られます。所得が高い人ほど効果は大きくなり、老後の資産形成がしやすいです。
控除額を適用するには、年末調整や確定申告時の申告が必要です。iDeCoを利用すれば、節税効果を活用しながら、効率的に将来のための資産を形成できます。
» iDeCoの節税効果を最大限にするコツ
会社以外の年金を確保できる

iDeCoに加入することで、個人的な年金の確保ができます。公的年金だけでは老後の生活資金が不足しがちですが、iDeCoによって不足分を補うことが可能です。掛金は自分で設定できるので、毎月の負担額と将来の年金額をコントロールできます。ライフプランに合わせて、柔軟に資産形成しましょう。
iDeCoは原則60歳までは引き出せないため、注意します。計画性のある掛金を設定してください。
転職しても保有資産を移換できる
転職しても保有資産を移換できることは、iDeCoの大きなメリットです。資産運用を中断せずに続けられます。転職先で新たにiDeCoに加入する際の移換先は以下のとおりです。
- 企業型DC
- 個人型iDeCo
前の職場で積み立てた資産を、新しい勤務先に移換することで、資産を分散せずに一元管理できます。ただし、手数料などの費用が発生する場合があるので注意しましょう。移換手続きは、新しい勤務先の企業型DCまたは個人型iDeCoで行います。移換手続きには一定の期間を要するため、早めの手続きをおすすめです。
転職時に資産を移換しない場合は、原則として資産の運用はそのまま続きます。転職先で資産管理が複雑にならないように、移換することがおすすめです。
会社員がiDeCoに加入するデメリット

会社員がiDeCoに加入する際は、以下のデメリットがあります。
- 転職先によってiDeCoの掛金の上限額が変動する可能性がある
- 保有資産を持ち運ぶ場合は一旦資産を売却しなければならない
- 受取時に全ての税制優遇を受けられない可能性がある
転職先によってiDeCoの掛金の上限額が変動する可能性がある
転職先によって、iDeCoの掛金の上限額が変動する可能性があります。転職先の企業年金制度によって、iDeCoの掛金上限額が異なることが理由です。転職先の企業が企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入しているかどうかで、掛け金上限額は変わります。
企業型DCに加入している場合と、していない場合の掛金の上限額は以下のとおりです。
- 加入している場合は月額20,000円
- 加入していない場合は月額23,000円
転職時には、上限額に合わせてiDeCoの掛金を見直しましょう。
保有資産を持ち運ぶ場合は一旦資産を売却しなければならない

転職などの理由で保有資産を持ち運ぶ場合は、一旦資産を売却しなければなりません。資産は直接的に移動ができないからです。保有している資産を売却し、その後に新しい口座で再購入する必要があります。保有資産を移動する際は、売却手数料が発生する可能性があるため注意が必要です。
売却時と再購入時に売却益が発生する場合、利益に対する税金がかかります。保有資産を持ち運ぶ際には、慎重な計画と準備が必要です。手続きの手間や費用、リスクを理解し、最適な方法を選ぶ必要があります。
売却後に再購入する際は、価格が変動するリスクも避けられません。再購入時に価格が上がっている場合は、同じ資産を購入するために、より多くの資金が必要になります。
受取時に全ての税制優遇を受けられない可能性がある
iDeCoの受取方法によっては、全ての税制優遇を受けられない可能性があります。iDeCoの受取が退職金と合算されて、控除額が減少し、課税対象が増える場合があるからです。年金形式で分割して受け取る場合は、他の年金収入と合算されて控除が減少し、税額が増えるリスクもあります。
iDeCoを受け取る際には、自身にとって最適な受取方法の検討が重要です。最適な受取方法は人によって変わるため、専門家への相談をおすすめします。
» iDeCoは受け取り方が重要!最適な選び方を解説
会社員がiDeCoに加入するための条件
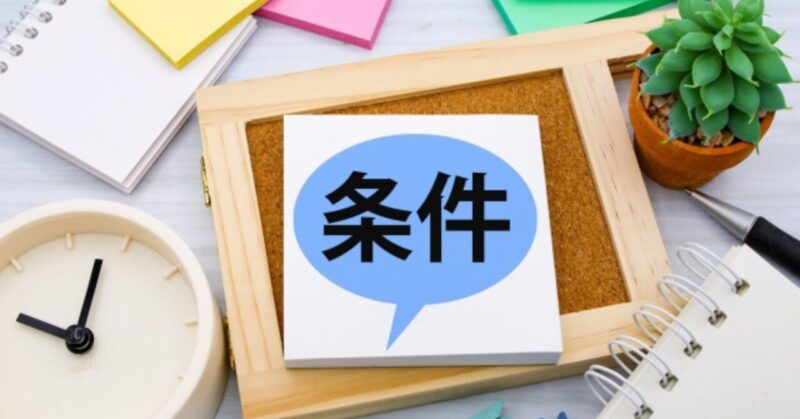
会社員がiDeCoに加入するための条件を紹介します。
会社員がiDeCoに加入できるケース
会社員がiDeCoに加入するには以下の条件を、勤め先の企業で満たしている必要があります。
- 確定拠出年金制度に対応している
- 企業型確定拠出年金に加入している
- iDeCoの掛金を拠出しない
- iDeCoの掛金の拠出を認めている
以上の条件を満たすことで、会社員でもiDeCoに加入することが可能です。企業の制度や方針によりますが、会社員はiDeCoに加入できるケースが多いです。2017年1月からは公務員の加入も認められています。
会社員がiDeCoに加入できないケース
会社員であっても、以下のような場合はiDeCoに加入できません。
- 厚生年金加入者ではない
- 企業型確定拠出年金に加入している
- 勤務先がiDeCoを認めていない
- 国民年金保険料を滞納している
- 65歳以上である
- 過去にiDeCo加入資格を喪失している
以上の場合は、iDeCoに加入できないので注意が必要です。
会社員のiDeCoの始め方

iDeCoを始めるためには、いくつかのステップがあります。会社員のiDeCoの始め方は以下のとおりです。
- 加入資格があるかを確認する
- 掛金の上限額を確認して掛金を設定する
- 運用商品を選ぶ
- 口座を開設する金融機関を選ぶ
- 口座開設の申し込みをする
- 掛け金が引き落とされる
加入資格があるかを確認する
加入資格があるかの確認は、iDeCoを始めるための第一歩です。加入資格の条件は以下のとおりです。
- 日本国内に住所がある
- 年齢が20歳以上60歳未満である
- 厚生年金保険の被保険者である
企業年金に加入している場合は、勤め先の企業がiDeCoへの加入を許可しているかを確認しましょう。企業によってはiDeCoの加入を制限しているからです。農業者年金に加入している場合も、iDeCoには加入できません。自身の状況や企業の条件の確認が重要です。
掛金の上限額を確認して掛金を設定する

上限額を超える掛金は設定できません。勤務先に企業型確定拠出年金がある場合は、月額20,000円が上限になります。企業型確定拠出年金がない場合は、掛金の上限額は月額23,000円です。厚生年金基金や確定給付企業年金がある場合も上限額が変わります。
掛金は月単位で設定できて、年単位で変更が可能です。転職などで勤務先が変わる場合は、上限額を調整できます。掛金の上限額を正確に把握し、無理なくiDeCoを運用しましょう。
» iDeCoはいくらから始める?自分に合った掛け金の設定方法
運用商品を選ぶ
iDeCoの運用商品を選ぶ際は、自分のリスク許容度が重要になります。リスク許容度とは、投資による損失をどの程度まで受け入れられるかの目安です。リスク許容度に合わせて運用商品を選ぶことが大切です。運用商品には主に以下の種類があります。
- 定期預金
- 投資信託
- 債券
- 株式
- 不動産投資信託(REIT)
リスクを避けたい場合は定期預金や債券が適しています。元本保証があるため、資産を減らすリスクを最小限に抑えることが可能です。高いリターンを狙いたい場合は、株式やREITを選びましょう。ただし、価格変動が大きく、損失のリスクも高まります。
リスクとリターンのバランスを考慮した、複数の運用商品への分散投資がおすすめです。一つの投資が大きく損失を出しても、他の投資で補えて全体のリスクを低減できます。
» 大切な資産を減らさない!iDeCoの選び方と運用方法
口座を開設する金融機関を選ぶ
金融機関を選ぶ際に注意すべきポイントはいくつかあります。手数料が低い金融機関を選ぶことが重要です。無駄なコストを抑え、運用効率を高められます。運用商品が豊富な金融機関を選ぶこともおすすめです。投資先の選択肢が多いと、自分のリスク許容度に合わせて分散投資できます。以下のポイントも確認しましょう。
- サポート体制が充実している
- 金融機関の信頼性が高い
- 口座画面が使いやすい
困ったときにすぐに相談できるサポート体制があれば、初心者でも安心して利用できます。口座画面が使いやすいと、ストレスなく運用成果の確認ができます。大手金融機関や歴史のある金融機関は、信頼性が高いのでおすすめです。以上の点に考慮し、最適な金融機関を選びましょう。
口座開設の申し込みをする

口座開設の申し込みの手順は以下のとおりです。
- 本人確認書類を準備する
- オンラインか郵送で申し込み用紙を取得する
- 本人確認と申請書類を金融機関に提出する
- 口座開設完了の通知が届く
申込用紙は、金融機関のウェブサイトからダウンロードできることが多いです。金融機関によっては、オンライン上の手続きで完結します。口座開設完了の通知を受け取ることで、口座開設は正式に完了です。
» 資産形成に役立つiDeCoの基礎知識と注意点
掛け金が引き落とされる
iDeCoの掛け金は、毎月自動的に指定された口座から引き落とされます。引き落とし日は選んだ金融機関や契約内容によって異なるため、事前の確認が必要です。加入時に指定した口座から引き落とされます。残高不足で引き落としができなかった場合は、別途の手続きが必要です。
引き落とされた掛け金は、選んだ運用商品に投資されます。運用商品の投資状況は、毎月の明細書や金融機関のウェブサイトで確認できます。安心してiDeCoを続けるためにも、定期的な確認が重要です。
【年代別】会社員のiDeCoの節税効果シミュレーション
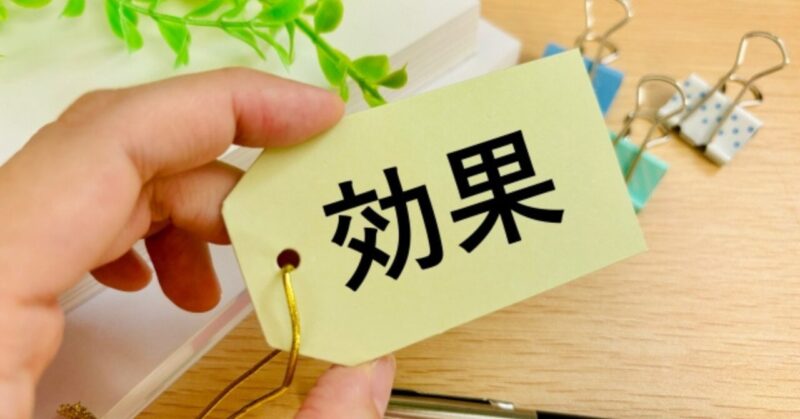
iDeCoは、加入する年代によって節税効果が大きく変わります。年代別の節税効果について詳しく解説します。
20代
20代の会社員がiDeCoに加入した場合、年間掛金は12万円が一般的です。所得控除による節税効果は、年間で約1.8万円です。iDeCoを20代から始めると、将来の年金額を大きく増やせます。長期間運用できて、複利効果が大きく働くからです。
20代のiDeCoの加入は、投資経験を積む機会にもなります。若いうちから投資の経験を積むことで、リスク管理や資産運用のスキルが身に付きます。長期間の運用でリスク分散がしやすく、目標到達も容易です。老後資金を計画的に準備できて、将来は安心です。
30代

30代になると生活と収入が安定し、投資に回せる余裕が出てきます。30代の会社員がiDeCoに加入した場合、年間掛金は24万円が一般的です。所得控除による節税効果は、年間で約3.6万円です。30代から始めることで、老後資金をより確実に準備できます。
30代は老後を意識し始めるタイミングでもあります。家族が増えるなど、将来のための資産形成が必要になる年代だからです。30代は投資リスクを取れる期間がまだ十分にあるため、リスク許容度が比較的高いことも特徴です。40代に比べて運用期間が長いため、複利効果も十分に期待できます。
30代になると余裕資金が大きくなり、掛金を増やしやすくなります。30代からのiDeCoへの加入はメリットが大きいです。
40代
40代からiDeCoに加入すれば、老後の安心感を大きく高められます。会社員ではiDeCoの年間掛金は24万円が上限ですが、フリーランスの場合は上限は81.6万円です。フリーランスの所得控除による節税効果は、最大で年間約12.4万円です。
40代になると収入がピークに達することが多く、所得税や住民税が高くなる傾向にあります。iDeCoの節税効果は大きいのでおすすめです。40代は教育費や住宅ローンの支払いが重なり、健康リスクも増加し始めるため、老後資金を本格的に考える必要があります。iDeCoは老後の助けになります。
まとめ
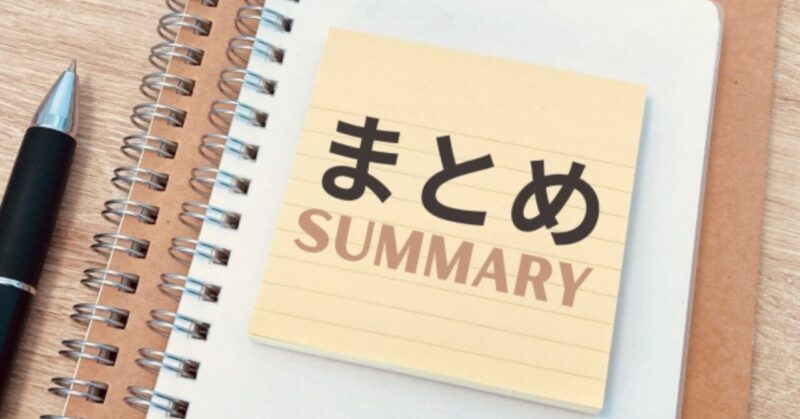
iDeCoは節税効果が高く、老後の資金を安定させるための有力な手段です。掛金が全額所得控除になるため、毎年の税金を減らせるメリットがあります。会社員の年間掛金の上限は24万円ですが、フリーランスは81.6万円です。
iDeCoは、転職しても保有資産を新しい職場に移換できますが、以下のデメリットがあります。
- 転職先によって掛金の上限額が異なる
- 保有資産を持ち運ぶ際に、一時的な売却が必要になる
- 受取時に、全ての税制優遇を受けれない可能性がある
iDeCoに加入する際はしっかりと条件を確認し、適切な運用商品を選ぶ必要があります。年代別に節税効果をシミュレーションすることも重要です。iDeCoをしっかりと理解することで、自身の状況に合わせた最適な資産形成が可能です。