PR
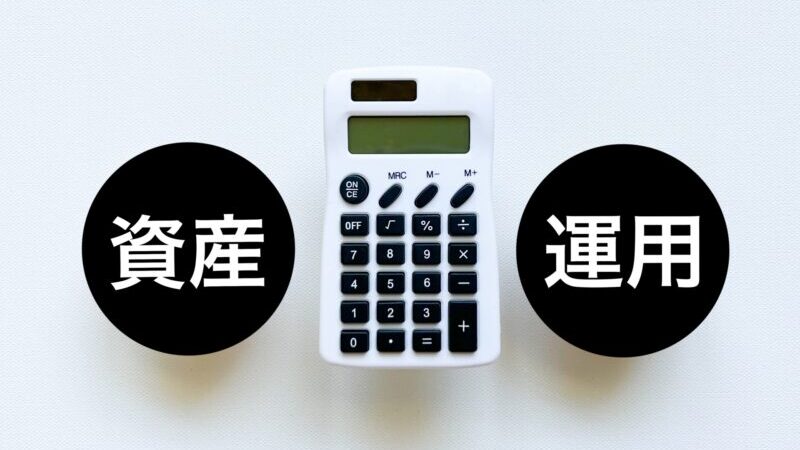
将来のためにお金を貯めたいが、専業主婦(夫)だと限界があると悩んでいる人は多いです。専業主婦(夫)でもiDeCo(確定拠出年金)を利用すれば、資産運用の効率化や税制優遇を受けられます。この記事では、専業主婦(夫)がiDeCoに加入するメリットやデメリット、始め方をわかりやすく解説します。
記事を読んで、専業主婦(夫)でも無理なくiDeCoを活用しましょう。iDeCoを始めると、将来の資金を効率良く増やし、税金を節約できます。
iDeCo(確定拠出年金)とは個人型の年金制度

iDeCoは、日本の公的年金制度の一環として導入された個人型の年金制度です。税制上の優遇を受けられるため、多くの人にとって魅力的な制度です。幅広い層が将来の生活資金を補完する手段として利用しています。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
iDeCoの仕組み
iDeCoは個人型確定拠出年金の略称で、自分で運用する年金制度です。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益が非課税なのが大きなメリットです。受取時にも節税できるため、将来的に節税効果が期待できます。毎月一定額を拠出します。限度額は職業によって異なるため、確認が必要です。
会社員や公務員、専業主婦など、職業に応じて設定されています。拠出期間は原則60歳までです。積み立てた資金を自分で選んだ運用商品で増やせます。運用商品の種類は豊富で、リスク許容度や投資経験に合わせて選べます。金融機関によって手数料が異なるため、選ぶ際には注意が必要です。
加入には口座管理手数料がかかります。60歳まで引き出せない点にも注意が必要です。受取方法は一時金か年金形式を選べるため、自分に合った形で受け取れます。
専業主婦(夫)もiDeCoに加入できる

専業主婦(夫)もiDeCoに加入できます。iDeCoは自分で積み立て、運用結果に応じて将来の受取額が決まる仕組みです。専業主婦(夫)でも、自分名義の年金を作り、将来の生活資金を準備可能です。専業主婦(夫)のiDeCo加入者は年々増加しており、多くの家庭が将来への備えを強化しています。
専業主婦(夫)のiDeCoの加入者数
専業主婦(夫)のiDeCo加入者数は着実に増加しています。2022年末時点で約12万人が加入しており、2021年末の約10万人から大幅に増加しました。加入者数の増加傾向は、iDeCoの制度やメリットが広く認知された結果です。専業主婦(夫)のiDeCo加入者は全体の約16%を占めています。
» iDeCo公式サイト(外部サイト)
専業主婦(夫)がiDeCoに加入するメリット
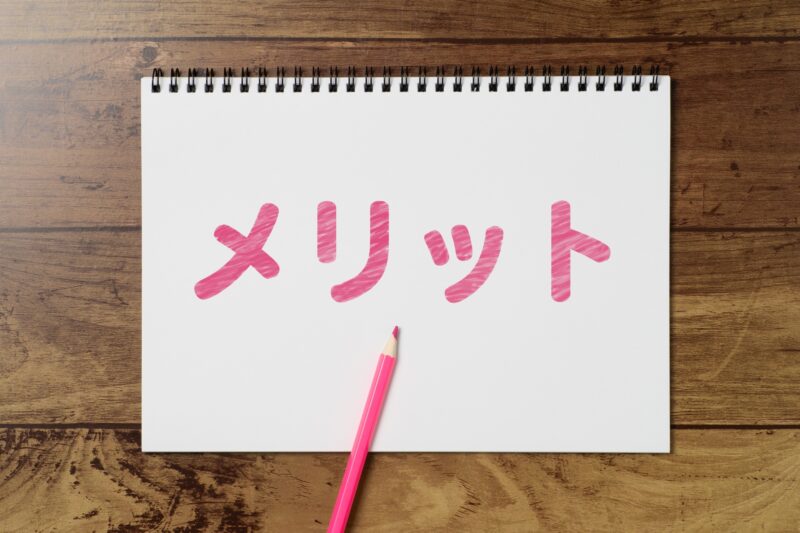
専業主婦(夫)がiDeCoに加入するメリットは多岐にわたります。専業主婦(夫)のiDeCo加入は、将来の経済的な安心を得るために重要です。主なメリットとして以下が挙げられます。
- 運用益が全額非課税になる
- 受取時に税制優遇を受けられる
- 自分名義の年金を作れる
運用益が全額非課税になる
iDeCoを活用すると、運用で得た利益が全額非課税になるメリットがあります。通常、投資で利益を得た場合、約20%の税金がかかります。しかし、iDeCoでは税金が免除されるため、運用益をすべて手元に残すことが可能です。
全額非課税になることで、長期的な資産形成において他の投資方法よりも有利な結果を得やすくなります。家庭の将来を見据えた堅実な資産運用を考える際、税制優遇を受けながら効率的に資産を増やせるのは大きな魅力です。
受取時に税制優遇を受けられる

iDeCoの受取時には税制優遇を受けられます。受取方法に応じて「退職所得控除」か「公的年金等控除」のいずれかを選択可能です。一時金として受け取る場合には「退職所得控除」が適用されます。退職所得控除は、勤続年数に応じて控除額が増えるため、長期間積み立てを行うほど節税効果が大きいです。
年金として受け取る場合には「公的年金等控除」が適用されます。公的年金等控除は年齢や年金受取額に応じて控除額が設定されており、公的年金と同様の優遇を受けられます。一時金と年金を併用して受け取れるため、それぞれの控除を組み合わせて節税が可能です。
» iDeCoは受け取り方が重要!最適な選び方を解説
自分名義の年金を作れる
iDeCoを利用すると、自分の名前で年金を積み立てられます。将来の老後資金を確保するために重要です。専業主婦や専業主夫でも、自分名義の年金を持てます。配偶者に依存せずに個別の資産形成ができ、離婚や配偶者の死亡などのリスクにも備えられます。経済的な独立と安心感を手に入れると、将来の不安の軽減が可能です。
専業主婦(夫)がiDeCoに加入するデメリット
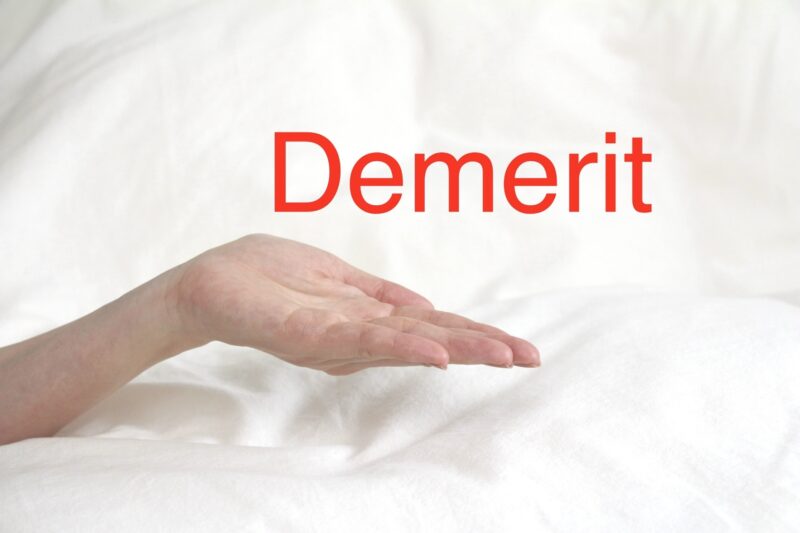
専業主婦(夫)がiDeCoに加入するデメリットはいくつかあります。iDeCoを利用する際にはリスクを理解し、計画的な運用が求められます。主なデメリットを以下で解説します。
原則60歳まで引き出せない
iDeCoは、原則として60歳まで引き出せません。老後資金の長期間にわたる確実な積み立てを目的としているためです。計画的な資産形成が促進されますが、急な出費が発生した場合には対応できません。
口座管理手数料が発生する

iDeCoを利用する際には、口座管理手数料が発生する点がデメリットです。手数料は金融機関が口座を管理するためのコストとして、避けられません。主な手数料として以下が挙げられます。
- 口座開設時の初期手数料
- 月額または年額の口座管理手数料
- JIS&T(年金積立金管理運用独立行政法人)への手数料
手数料の額は金融機関によって異なるため、事前の確認が重要です。iDeCoを始める際には、管理手数料がなるべく安い金融機関を選ぶと良いです。手数料の積み重ねが運用益に影響するため、少しでも費用を抑えましょう。
元本割れのリスクがある
iDeCoには元本割れのリスクがある点に注意が必要です。投資信託などの運用商品は市場の変動に左右され、資産が減る可能性があります。保守的な運用商品を選んでも、リスクの完全な排除はできません。長期的な運用でも元本保証はありません。
投資先のパフォーマンスが予想を下回った場合、元本は減少する恐れがあります。リスクを理解し、自分のリスク許容度に合った運用商品を選びましょう。
» iDeCoの投資信託のラインナップ
» iDeCoが元本割れする原因と対処法
専業主婦(夫)がiDeCoを最大限活用するためのポイント

専業主婦(夫)がiDeCoを最大限活用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。以下のポイントを押さえると、将来の資産形成に役立ちます。
- 無理のない範囲で長期的に積み立てる
- 自分にあった運用商品を選ぶ
- NISAと併用する
無理のない範囲で長期的に積み立てる
無理のない範囲で長期的に積み立てることが大切です。無理なく積み立てれば、日常生活に支障をきたさずに資産運用を続けられます。自分の収入や支出を見直し、毎月無理なく積み立てられる金額を設定しましょう。生活費や他の必要な支出を圧迫させずに、余裕資金を確保できます。
毎月の収入から固定費や変動費を差し引いた後、残った金額の一部を積み立てに回すと良いです。長期的な視点も重要です。短期間で大きなリターンを期待せず、長期的な目標に向かって積み立てると、短期的な市場の変動によるリスクを軽減できます。
定期的に積み立て状況を確認し、必要に応じて金額や運用方法を見直しましょう。無理のない範囲で長期的に積み立てると、安心して資産運用を続けられます。
自分にあった運用商品を選ぶ

自分にあった運用商品選びは、iDeCoで投資運用を成功させるために重要です。リスク許容度の把握が大切です。投資による損失をどれだけ受け入れられるかを把握すると、適切な投資商品を選びやすくなります。リスク許容度を理解したら、債券と株式のバランスを考えましょう。
債券は比較的リスクが低く、株式はリスクが高いですがリターンも大きいです。債券と株式のバランスを自分のリスク許容度に合わせて設定しましょう。運用商品の選択において手数料や信託報酬も確認する必要があります。手数料や信託報酬が高いと利益が減少するため、手数料が低く費用対効果の良い商品をおすすめします。
インデックスファンドとアクティブファンドの違いも理解しましょう。インデックスファンドは市場全体の動きを反映し、手数料は低めです。アクティブファンドは専門家が積極的に運用します。高いリターンを狙えますが、手数料は高いです。どちらが自分に合っているかを見極めてください。運用実績の調査も役立ちます。
商品の過去の運用実績が良好であれば、将来的にも安定したリターンが期待できます。分散投資も重要です。1つの投資商品に全額を投入すると、不調だった場合に大きな損失を被る可能性があります。複数の投資商品に分散して、リスクを減らしながら安定したリターンを得ましょう。
» iDeCoの手数料の種類と節約方法
» iDeCoを活用して効率的に運用するためのコツを解説
NISAと併用する
NISAとiDeCoを併用すると、非課税枠をより効果的に活用できます。iDeCoは老後資金に特化した制度ですが、NISAは一般的な投資にも利用できるため、運用の幅が広がります。NISAはiDeCoより早く資金を引き出せるため、短期的な資金ニーズに対応可能です。
NISAでリスクの低い商品を選び、iDeCoで長期運用向けの商品を選ぶと、リスクを分散できます。NISAとiDeCoを併用すると、両方の税制優遇を最大限に活用できます。短期的な資金確保と長期的な資産運用の両立ができ、より安定した将来の資金計画が可能です。
専業主婦(夫)のiDeCoの始め方

専業主婦(夫)がiDeCoを始めるためには、いくつかのステップを踏む必要があります。主なステップは以下のとおりです。
- 加入資格と掛金の上限額を確認する
- 掛金を設定する
- 金融機関を選ぶ
- 申し込み手続きを行う
加入資格と掛金の上限額を確認する
専業主婦(夫)がiDeCoに加入するためには、加入資格と掛金の上限額を確認する必要があります。iDeCoの加入資格は、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者と第2号被保険者、第3号被保険者が対象です。専業主婦(夫)は国民年金第3号被保険者に該当し、掛金の上限額は月額23,000円です。以下に加入資格と掛金の上限をまとめました。
| 加入者区分 | 加入資格 | 掛金上限(月額) |
| 自営業者(国民年金第1号被保険者) | 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者 農業、漁業、フリーランスなどを含む | 68,000円 |
| 専業主婦(主夫)(国民年金第3号被保険者) | 厚生年金に加入している配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の国民年金第3号被保険者 | 23,000円 |
| 会社員(国民年金第2号被保険者) | 厚生年金に加入している20歳以上60歳未満の会社員や公務員 会社が企業年金を実施しているかどうかにより掛金上限が異なる | 企業年金なし:23,000円 企業型DC加入者:20,000円 企業年金あり:12,000円 |
| 公務員(国民年金第2号被保険者) | 公務員で20歳以上60歳未満の国民年金第2号被保険者 | 12,000円 |
掛金を設定する

掛金を設定する際は、毎月の掛金額を決める必要があります。専業主婦(夫)の場合、掛金は月々5,000円から1,000円単位で設定できます。家庭の収入や支出を考慮し、無理のない範囲で設定しましょう。掛金は全額所得控除の対象になるため、節税効果が期待できます。
掛金は銀行口座から自動引き落としされるため、手軽に始められます。経済状況が変わった場合は、一時停止が可能です。毎月10,000円の掛金を設定した場合、年間で120,000円の所得控除となり、税負担が軽減されます。掛金の変更は年に1回できて、必要に応じて調整することが可能です。
掛金を変更する際には、金融機関への手続きが必要なため、事前に確認しておくとスムーズです。長期的な資産形成を考えて、計画的に掛け金を設定しましょう。長期にわたって積み立てれば、老後資金をしっかりと確保できます。
金融機関を選ぶ
金融機関を選ぶ際には、手数料の比較が重要です。運用期間が長いほど手数料の差が資産に大きく影響するため、少しの差でも合計額には大きな違いが出ます。取扱商品のラインナップを確認し、自分が運用したい商品がそろっているかを見ると良いです。サポート体制やサービスの質にも注目しましょう。
困ったときにすぐに相談できる窓口があるか、問い合わせへの対応が迅速かどうかを確認すると安心です。金融機関の信頼性や実績も考慮すべき点です。長い歴史や多くの利用者から信頼を得ている金融機関は、安心して利用できます。インターネットバンキングの利便性もチェックしましょう。
日常的に利用する機会が多いため、使いやすさや機能の充実度が資産運用の快適さに影響します。キャンペーンや特典も見逃せません。新規加入者向けの特典や期間限定のキャンペーンを活用すれば、さらにお得に利用できます。他の利用者の口コミや評価を参考にするのも有益です。
利用者の意見や経験は、金融機関選びに役立ちます。さまざまなポイントを総合的に考慮し、最適な金融機関を選びましょう。
申し込み手続きを行う
iDeCo申し込み手続きの流れは以下のとおりです。
- 申し込み書を取り寄せるか、金融機関のウェブサイトからダウンロードする
- 個人情報や掛金額、運用商品などの必要事項を記入する
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)を準備する
- 勤務先がある場合は、会社に証明書を依頼する
- 書類を郵送またはオンラインで提出する
- 金融機関からの審査結果を待つ
- 初回掛金の引き落とし設定を確認する
- 口座開設完了通知を受け取る
- 運用商品の選定を確定する
iDeCoのよくある質問
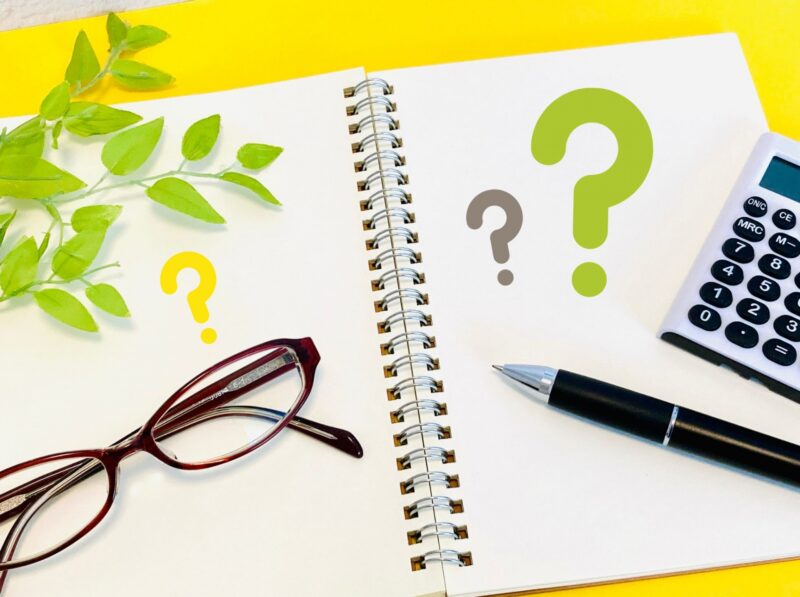
iDeCoに関するよくある質問をまとめました。専業主婦(夫)でiDeCoを始めたいと考えている人は参考にしてください。
iDeCoの掛金はいつ変更できる?
iDeCoの掛金は、年に1回変更できます。iDeCoの運用に柔軟性を持たせるための重要な仕組みです。掛金を変更したい場合は、所定の変更届を金融機関に提出します。金融機関によって提出期限や変更が反映される時期が異なるため、事前の確認が必要です。
変更届を提出してから反映されるまでに、数か月かかる場合があるため、計画的に行いましょう。年に1回のタイミングをうまく活用すると、収入や支出に合わせた最適な掛金設定が可能です。
退職金とiDeCoの関係は?
iDeCoの受取時には、退職金と同じ「退職所得控除」が適用されます。退職金とiDeCoの受取金額を合算して控除額を計算する必要があります。退職金の受取時期とiDeCoの受取時期の調整が重要です。退職金が多い場合、iDeCoの一時金としての受取は、控除の恩恵が少なくなる可能性もあります。
受取方法によって税制優遇の範囲が異なります。iDeCoを一時金として受け取るか、年金形式で受け取るかを慎重に検討しましょう。退職金とiDeCoの関係を理解し、最適なタイミングの受取を計画すると、税負担を減らせます。
まとめ
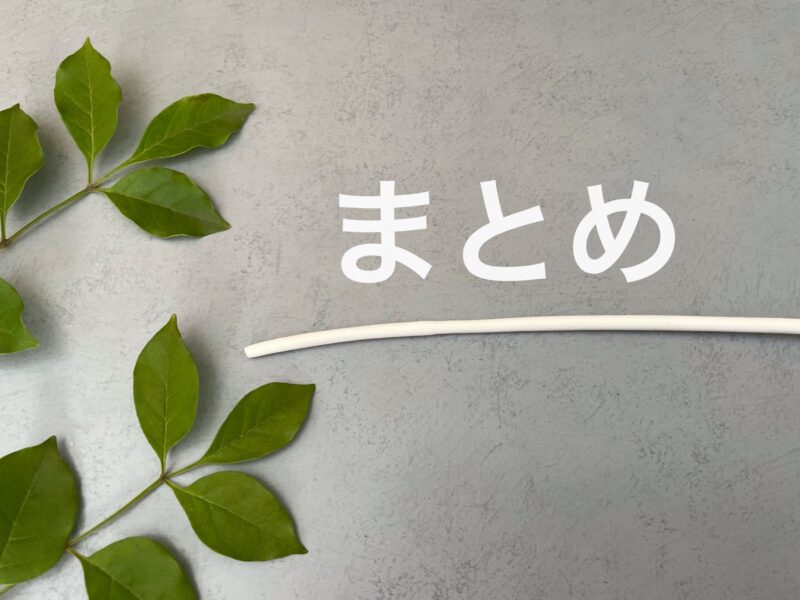
iDeCoは、老後資金を準備するための個人型確定拠出年金制度です。専業主婦(夫)も加入できて、運用益が全額非課税であり、受取時に税制優遇を受けられるメリットもあります。60歳まで引き出せない点や口座管理手数料が発生する点、元本割れのリスクがある点を理解しておくことも大切です。
自分に合った運用商品を選び、無理のない範囲で長期的に積み立てましょう。NISAと併用すると、非課税枠を最大限活用できます。加入資格や掛金の上限額を確認したうえで、適切な掛金を設定してください。金融機関を選んで、申し込み手続きを進めましょう。