PR
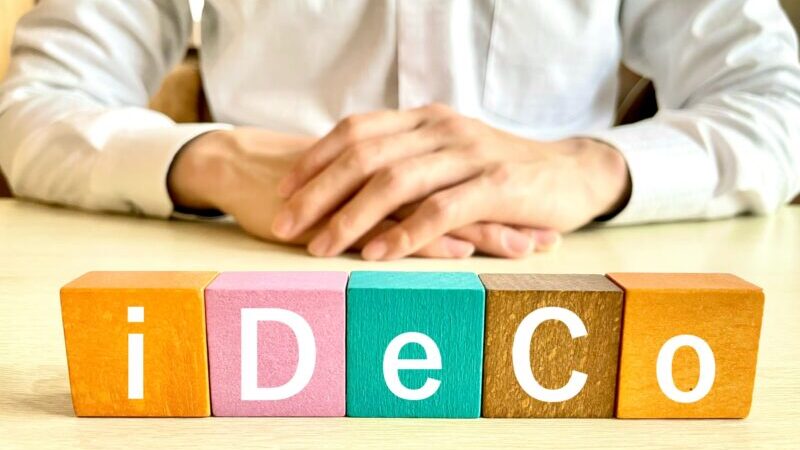
転職した場合のiDeCoの取り扱いについて、多くの人が悩んでいます。iDeCoは将来のために資産を形成する私的年金制度ですが、転職時には手続きや運用方法に戸惑う人が多いのが現状です。この記事では、転職時のiDeCoの取り扱いについて詳しく解説します。
記事を読めば、転職後のiDeCoの手続き方法や金融機関の選び方、よくある質問への回答などがわかります。転職を考えている人や、既に転職をした人は、スムーズにiDeCoを管理し続けることが可能です。
iDeCo(確定拠出年金)とは投資商品で資産を形成する年金制度

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自身で選んだ投資商品を使って資産を形成する私的年金制度です。iDeCoの加入資格やiDeCoのメリット、デメリットについて解説します。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
iDeCoの加入資格
iDeCoに加入するための条件は、20歳以上60歳未満の日本国民であることです。自営業者やフリーランス、会社員、公務員、専業主婦(夫)などの幅広い層が含まれます。海外に住んでいても、日本国内に住所がある場合は加入できます。加入者の状況に応じて、将来のための資産の計画的な積み立てが可能です。
» iDeCoの加入資格は?基本情報から手続き方法まで詳しく解説
» iDeCoは何歳から始められるかを解説
会社員であれば、企業型確定拠出年金と併用して資産を増やせます。自営業者やフリーランスは、収入の変動に応じて掛け金を柔軟に設定できるため、リスクの分散が可能です。専業主婦(夫)は家庭の収入に応じて積み立てをすると、将来の生活に安心感が生まれます。
» 会社員がiDeCoに入るメリットと年代別の節税効果を解説
iDeCoのメリット

iDeCoには多くのメリットとデメリットがあります。iDeCoのメリットは以下のとおりです。
- 掛け金が全額所得控除の対象になる
- 年末調整や確定申告で、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されるため、節税効果が高いことが特徴です。所得がある人であれば、誰でも利用できます。
- 運用益は非課税で再投資される
- iDeCoの運用益は、原則として非課税です。利益が出ても税金がかかりません。複利効果が働き、長期間の運用によって資産が大きく増加する可能性があります。
- 受取時にも税制優遇がある
- 退職金として受け取る場合は退職所得控除が適用され、年金として受け取る場合は公的年金等控除が適用されます。
- 自身で運用商品を選べる
- 投資信託や定期預金など、多様な商品から選択できるので、自分のリスク許容度や投資目標に応じた運用が可能です。
- 自営業やフリーランスも加入できる
- 固定収入がない場合でも、老後資金形成の手段として有効に活用できます。
iDeCoのデメリット
iDeCoにはいくつかのデメリットもあります。iDeCoのデメリットは以下のとおりです。
- 掛け金の上限が決められている
- 大きな金額を一度に積み立てられません。会社員の場合は、月額2〜2万3,000円までが上限です。上限を超える掛け金は、所得控除の対象外となります。
- 60歳まで原則的に引き出せない
- 急な病気や怪我など、予期せぬ出費が発生した場合、iDeCoの資金をすぐに利用することはできません。
- 手数料がかかる
- iDeCo口座を維持するためにかかる手数料や、投資信託などの運用商品に投資する際に、運用会社に支払う手数料がかかります。
- 元本割れのリスクがある
- 運用商品が市場の影響を受けるためです。投資信託のようなリスクの高い商品を選択する場合は、慎重に判断しましょう。
- 掛け金の変更や中断に手続きが必要である
- 途中で掛け金の変更や中断ができますが、手続きが必要であり、手間がかかる点もデメリットです。状況に応じて柔軟に対応するためには、手続きを迅速に行う準備が必要になります。
メリットとデメリットを理解したうえでiDeCoを活用すると、効率的に老後資金を積み立てられます。
転職時のiDeCoの取り扱い

転職時には、iDeCoの運用を継続することが可能です。ただし、転職先の規定によって取り扱いが異なる場合がある点に注意しましょう。転職先の規定の違いによる転職時のiDeCoの取り扱いについて解説します。
転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)がある場合
転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)がある場合、iDeCoから企業型DCへの移換手続きを行いましょう。企業型DCを運営する企業に必要書類を提出し、手続きを進めます。企業型DCのメリットを生かしながら資産を一元管理できるため、管理が簡単になります。
企業型DCに加入後も、引き続きiDeCoに加入し、掛け金の拠出が可能です。企業型DCとiDeCoを同時に利用する場合、掛け金の合計額が税制上の上限を超えないように調整することが大事です。企業型DCの掛け金が多ければ、iDeCoに拠出できる金額が減る場合があります。
企業型DCの受取口座を、転職先の口座に移換する手続きが必要になる場合もあります。転職先の企業型DCに関する情報を、事前に確認しておきましょう。運用商品や手数料の確認も重要です。転職先の企業型DCの運用商品や手数料を確認し、自分の投資方針やコストに見合うか検討しましょう。
コストを抑えられれば、効率的な資産運用が可能です。
転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)がない場合
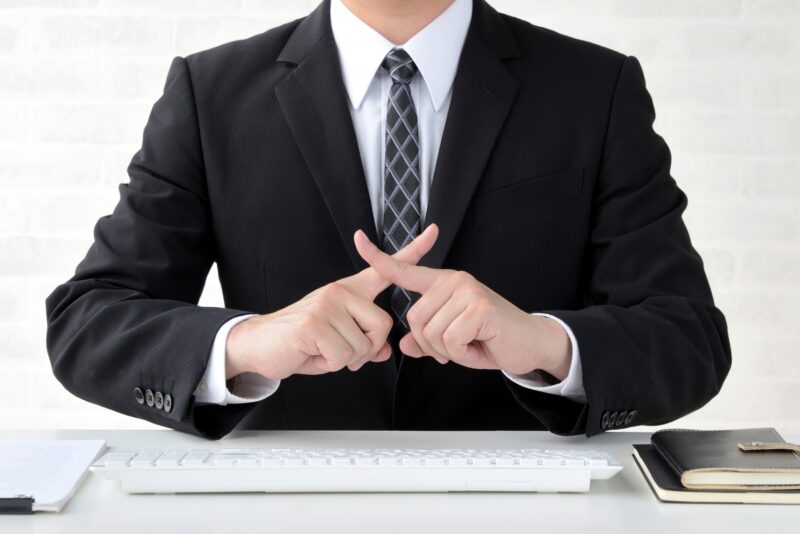
企業型確定拠出年金(企業型DC)がある会社からない会社へ転職する場合、引き続きiDeCoへの加入が可能です。企業型DCをiDeCoに移換する手続きを行いましょう。企業型DCの残高をそのまま保持できないためです。手続きには一定の期間がかかる場合があるため、早めに対応しましょう。
手順は以下のとおりです。
- 企業型DCの運営管理機関に連絡する
- 必要な書類を取得する
- iDeCoの運用商品を選択する
移換手続きには国民年金基金連合会への手数料が発生します。iDeCoへの移換後は自身で運用する商品を選べるため、柔軟に資産形成を進められます。自身で掛け金を設定し、収入やライフスタイルに合わせて調整が可能です。転職先に企業型DCがない場合でも、将来の年金資産をしっかりと形成できます。
企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する場合
企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する場合、自身で手続きを行う必要があります。企業型確定拠出年金の情報と、iDeCoの加入資格を確認してから進めることが大切です。移換手続きには「個人型年金移換申出書」を使用します。企業型確定拠出年金の運営管理機関から申出書を取り寄せ、必要事項を記入しましょう。
iDeCoの加入手続きを行う金融機関に提出します。手続きには数か月かかる場合があり、一時的に運用が停止する場合もあるので注意が必要です。手続きが完了した後はiDeCoの規定に従って、運用商品を選択できるようになります。移換時には手数料や解約金が発生する場合もあるので事前に確認が必要です。
移換後も税制上の優遇措置が適用されるため、安心して運用を続けられます。ただし、企業型確定拠出年金とiDeCoの違いやそれぞれのメリットをしっかり理解しておくことが重要です。
自営業やフリーランスになる場合
自営業やフリーランスになる場合、引き続きiDeCoへの加入が可能です。自営業やフリーランスは企業年金に加入できないため、公的年金だけでは老後資金が不足する可能性があります。iDeCoに加入するためには自分で手続きを行う必要があります。
掛け金の上限は月額6万8,000円で、小規模企業共済と併用することも可能です。
» 個人事業主にiDeCoはおすすめ?基本知識や始め方を解説
公務員になる場合

公務員になる場合もiDeCoに加入できます。ただし、加入には職場の許可や手続きが必要です。手続きの内容は一般企業とは異なる部分があるため、勤務先の人事部門に相談しましょう。iDeCoの掛け金は月額2万円まで拠出できます。
» 公務員がiDeCoで効率的に資産を増やす方法を解説
専業主婦(夫)になる場合
専業主婦(夫)になる場合、iDeCoに引き続き加入できます。専業主婦(夫)のiDeCoの掛け金は、月額最大2万3,000円まで積み立てが可能です。専業主婦(夫)が月額2万3,000円の掛け金を拠出する場合、年間で約27万円の所得控除を受け取れます。
家計全体での資産形成の戦略として活用することが大切です。資産運用の基本を学び、リスクを適切に管理することが求められます。家族と相談しながら資産形成の戦略を立てましょう。
» iDeCoの節税効果を最大限にするコツ
» 節税メリット大!iDeCoで主婦(夫)が賢く貯蓄する方法
転職時におけるiDeCoの具体的な手続き

転職時におけるiDeCoの具体的な手続きは、いくつかのステップを踏む必要があります。必要な書類やインターネットでの手続き方法、郵送での手続き方法について解説します。
必要な書類
転職時にiDeCoの手続きを行う際には、いくつかの書類が必要です。書類を揃えておくと、スムーズに手続きを進められます。必要な書類は以下のとおりです。
- 転職前の事業所からの移換証明書
- 現在の企業型確定拠出年金(企業型DC)の状況を証明するための書類です。
- 新たな事業所の加入者資格確認書
- 新しい職場での企業型DCの加入資格を確認するために使われます。
- 個人別管理資産の移換に関する同意書
- 新しい職場での企業型DCの加入資格を確認するために使われます。
- 個人別管理資産の移換に関する同意書
- 現在の年金資産を新しいプランに移換することへの同意を示すことが可能です。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 年金番号を確認するために使われます。
- iDeCo加入申込書
- iDeCoの新規加入手続きを行うために必要です。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 本人確認ができる書類を提出すると、手続きが正式に行われます。
- 金融機関の口座情報
- 掛け金の引き落とし先となる口座情報を提供するためです。
以上の書類を準備すると、iDeCoの手続きを円滑に進められます。
インターネットでの手続き方法

インターネットでの手続き方法は、自宅から簡単に進められるため便利です。手続き方法は以下のとおりです。
- 金融機関の公式ウェブサイトにアクセス
- ログイン画面から個人アカウントにログイン
- メニューから「iDeCo」や「確定拠出年金」を選択
- 見つからない場合は「サイト内検索機能」で検索
- 「転職手続き」や「移換手続き」をクリック
- フォームに必要な情報を入力
- 必要書類を郵送またはアップロード
- 送信ボタンをクリック
手続き完了の確認メールが届くため、大切に保存しておきましょう。インターネットでの手続きは完了です。
郵送での手続き方法
郵送でのiDeCoの手続き方法は、パソコンやスマートフォンの操作が苦手な人にとってハードルが低い方法です。必要書類は「個人型年金加入者登録確認書」「転職先企業からの企業型年金加入証明書」「年金手帳」などがあります。書類を揃えたら、加入している金融機関に転職の旨を伝えましょう。
金融機関から送付される「加入者変更届」などの書類を受け取ったら、次のステップに進みます。受け取った書類に必要事項を記入し、署名し押印しましょう。記入した書類と必要書類を同封し、指定の住所へ郵送します。郵送先の住所は金融機関から案内されるので、忘れず確認しましょう。
郵送後は、金融機関からの連絡を待ちます。通常は、金融機関から通知が届いたら手続き完了になります。郵送での手続きは少々手間がかかりますが、確実に行うとスムーズにiDeCoの変更手続きを終えることが可能です。
転職時にiDeCoの金融機関を選ぶポイント

転職時にiDeCoの金融機関を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。以下のポイントを押さえて、自分に合った金融機関を選ぶことが、転職時のiDeCoの運用を成功させる鍵になります。
- 口座管理手数料や信託報酬が安い
- 運用商品のバリエーションが多い
- 利便性が高くサービス内容が良い
口座管理手数料や信託報酬が安い
iDeCoの運用を成功させるためには、口座管理手数料や信託報酬が安い金融機関を選ぶことが重要です。手数料や信託報酬は、長期運用において最終的な資産額に大きく影響するため、なるべく低く抑えましょう。金融機関ごとに設定されている口座管理手数料を比較してみてください。
無料や低額の金融機関を選ぶと、手数料の負担を減らせます。運用益を最大化するためには、運用商品のコストである信託報酬が低い金融機関を選ぶことも重要です。 信託報酬が低いインデックスファンドは、長期的な資産形成に効果的です。
金融機関の手数料体系や信託報酬は定期的に見直しが行われるため、最新の情報を常に確認しましょう。より有利な条件での運用が可能です。
» iDeCoの手数料の種類と節約方法
運用商品のバリエーションが多い

運用商品のバリエーションが多いと、投資目標やリスク許容度に合った商品を選択できるため、柔軟な投資が可能になります。以下の多くの選択肢があります。
- 国内外の株式ファンド
- 国内外の債券ファンド
- バランス型ファンド
- インデックスファンド
- アクティブファンド
- REIT(不動産投資信託)
- コモディティファンド
- ESGファンド(環境・社会・ガバナンス重視)
- フレキシブルファンド(柔軟運用型)
- ターゲットイヤーファンド(年齢に応じた運用)
債券ファンドで堅実な運用をしたい、株式ファンドで積極的な運用をしたいなど、投資目標に合わせた商品選択が可能です。
» iDeCoの投資信託のラインナップ
利便性が高くサービス内容が良い
転職時にiDeCoの金融機関を選ぶ際は、利便性の高さとサービス内容の良さを重視しましょう。使いやすい公式サイトやアプリは、操作ミスや手間を減らし、時間効率を高めます。モバイル対応であれば、場所を選ばずにiDeCoを管理できます。
24時間対応のカスタマーサポートがある金融機関を選ぶと、困ったときにすぐに相談できて安心です。多言語対応が提供されていると、日本語が苦手人でも安心して利用できます。自動リバランス機能が提供されている場合、投資ポートフォリオのバランスを自動で調整してくれます。
専門知識がなくても安心して運用することが可能です。サービスの充実した金融機関では、定期的な投資アドバイスやセミナーなども提供しています。最新の投資情報や知識を得られるため、より賢明な投資判断が可能になります。
転職時のiDeCoについてよくある質問
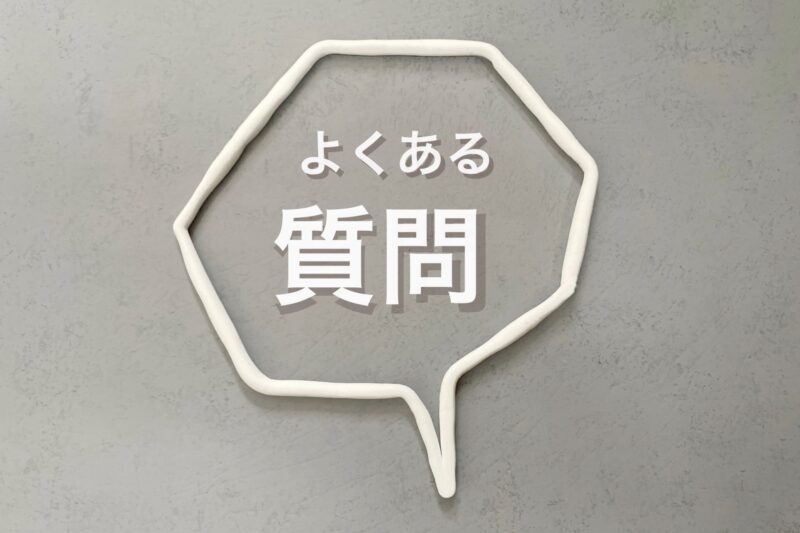
転職時のiDeCoの取り扱いについて疑問を持つ人は多くいます。転職時のiDeCoについてよくある質問は以下のとおりです。
- 転職後に掛け金は変更できる?
- 収入減で掛け金の拠出が難しくなったときはどうなる?
- 育休中の掛け金はどうなる?
転職後に掛け金は変更できる?
転職後もiDeCoの掛け金は変更可能です。iDeCoは、転職などのライフスタイルの変化に対応できる柔軟な制度になっています。ただし、掛け金の変更は年1回までかつ上限額が職業や企業年金によって異なる点に注意してください。
転職後に掛け金を変更する手続きは、金融機関を通して行います。書類で手続きする場合は、必要書類を金融機関に提出します。インターネットで手続きする場合は、金融機関の専用サイトから行うことが可能です。転職後も自分のライフスタイルや収入状況に応じた掛け金の設定ができるようになります。
転職後に掛け金の変更を検討している場合は、早めに手続きを進めましょう。新しい環境でiDeCoをスムーズに活用し続けられます。
収入減で掛け金の拠出が難しくなったときはどうなる?

収入が減って掛け金の拠出が難しくなった場合、以下の選択肢があります。
- 掛け金を減額する
- 自分の収入状況に合わせて自由に減額できます。拠出の負担を軽減することが可能です。制度の継続が可能となり、老後資金の準備を続けられます。
- 一時的に掛け金の拠出を停止する
- 収入が回復する見込みがある場合は、一時的に掛け金の拠出を停止できます。積立期間が短くなるため、老後資金の準備が遅れる可能性があることに注意が必要です。
- 金融機関に相談する
- iDeCoの運用や、収入減への対応について、専門家のアドバイスを受けることができます。他の金融商品への変更や、より適切な運用方法を提案してもらえる可能性があります。
- ライフプランを見直す
- 収支のバランスを見直し、無理のないプランを立てると、安定した家計管理が可能です。
- 他の資産運用方法を検討する
- iDeCoの運用や、収入減への対応について、専門家のアドバイスを受けることができます。複数の資産に分散投資すると、リスクの軽減が可能です。
育休中の掛け金はどうなる?
育休中の掛け金については、いくつか注意点があります。育休中は給与が支給されないため、企業が負担するiDeCoの掛け金も原則として停止します。ただし、自分で掛け金を拠出する場合は、育休中でもiDeCoを継続することが可能です。
掛け金を継続したい場合は、育休に入る前に、掛け金を継続する希望を会社へ伝え、必要な書類を提出します。手続きを行わない場合、育休期間中の掛け金は自動的に停止されるため注意してください。育休が終了し、通常の給与支給が再開されると同時に、企業負担の掛け金も再開されます。
育休中の掛け金に関する手続きは重要です。適切に手続きを行うと、育休期間中も安定した資産形成が可能になります。育休に入る前に、事前に準備を整え、必要な手続きを忘れずに行いましょう。
まとめ

iDeCoは老後資金の準備に役立つ私的年金制度です。転職時には企業型確定拠出年金の有無によって取り扱い方法が異なるため、注意が必要です。企業型DCがない場合は自分でiDeCoへの移換手続きを行う必要があります。転職後の掛け金変更や収入減に対する対策も、事前に知っておくと安心です。
口座管理手数料や信託報酬が安い金融機関を選ぶと、長期的な資産形成における費用を節約できます。運用商品のバリエーションやサービスの利便性も考慮して、自身に合った金融機関の選択が重要です。