PR
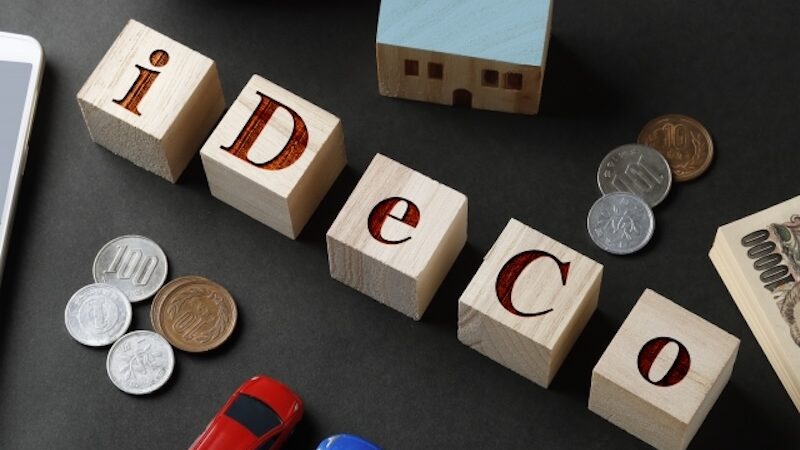
- 「iDeCoに興味はあるけれど、元本割れが心配…」
- 「フリーランスとして、自分で老後資金に備えたい」
元本割れや老後資金の悩みをお持ちの方は多いです。確定拠出年金であるiDeCoは、老後の資産形成に有効な手段ですが、元本割れのリスクが存在します。この記事では、iDeCoの基本から元本割れのリスクと対策方法を解説します。
記事を読み、元本割れを避け、安心して老後資金を増やしましょう。リスクを理解しつつ適切な商品選びができ、安心して運用を続けられる知識が身につきます。
iDeCo(確定拠出年金)とは自分で選んだ商品に投資すること

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分自身で選んだ運用商品に拠出金を投資する制度です。運用成果に応じて年金を受け取れます。節税効果と非課税運用益のメリットが大きく、年金受給に有利です。その他の特徴は以下のとおりです。
- 掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果が高い
- 運用益が非課税であるため、効率的に資産が増える
- 受け取る年金や一時金にも税制優遇措置があるため、将来の資産形成に役立つ
- 会社員、専業主婦(夫)まで職業に関わらず加入できる
- 金融機関によって手数料や商品ラインナップが異なる
- 20歳以上60歳未満の日本国内居住者であれば誰でも加入できる
毎月の掛金は最低5,000円から最大68,000円まで設定できます。積立金の引き出しは原則60歳からで、長期的な資産形成が目的です。
iDeCoのメリット
iDeCoのメリットは、税負担が軽減される点です。所得控除が受けられ、年末調整や確定申告の際に税金が戻ってきます。勤務先の企業年金との併用が可能なので、多角的に資産形成を進められます。具体的なメリットは以下のとおりです。
- 税負担の軽減
- 運用益の非課税
- 受け取り時の税制優遇
- 多様な投資選択肢
- 強制的な毎月の積立
- 企業年金との併用
- 運用益が非課税で投資可能
受け取るときにも税制優遇があります。一時金として受け取る場合と、年金形式で受け取る場合では税制優遇が異なります。老後の安定した収入源を確保して、年金受給額を増やしてください。
iDeCoで投資の選択肢を広げ、自分に合った運用をしましょう。多様な金融商品から選べるため、リスク許容度に応じた運用が可能です。強制的に毎月の積み立てが行われ、長期的な資産形成に繋がります。
iDeCoのデメリット
iDeCoにはデメリットもあります。デメリットを理解した上で、iDeCoが適しているかを検討しましょう。デメリットは以下のようになります。
- 運用成績が悪いと元本割れのリスクがある
- 原則として60歳まで引き出せない
- 投資商品の選択肢が限られているため、自分に合った投資商品を見つけるのが困難である
- 加入時と運用中には手数料がかかる
- 将来的に税制優遇が変更される可能性もある
- 一部の企業年金や公務員は加入できない
元本割れとは投資した金額が減少すること
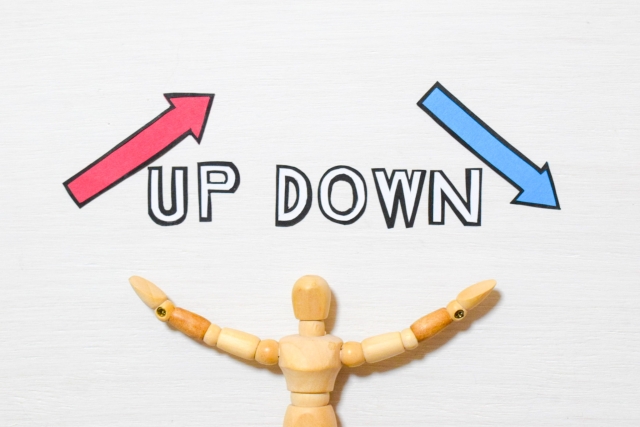
iDeCoの元本割れとは、投資した金額が減少することです。市場の変動や経済状況の変化により、資産価値が下がります。投資信託や株式など価格が変動する商品で元本割れが発生しやすいです。
元本確保型の商品でも、手数料やインフレの影響で元本割れのリスクがあります。長期間運用でリスクを分散できますが、確実な対策ではありません。
元本割れを完全には防げないため、リスクの理解が重要です。
iDeCoの元本割れの影響
iDeCoの元本割れは、退職後の生活に影響します。具体的には以下のとおりです。
- 老後資金の減少
- 退職後の生活設計の見直しが必要
- 他の収入源が必要
- 精神的なストレスの増加
元本割れが起きると、資産形成の見直しが必要です。他の投資や貯蓄計画にも影響が出ます。リスクの少ない方法を選ぶなど、投資先や貯蓄方法の見直しが必要です。時間と労力が求められます。
元本割れの可能性があるiDeCoの商品
市場の変動に影響を受けやすく、元本割れの可能性があるiDeCoの商品があります。具体的には以下のとおりです。
- 株式型投資信託
- 企業の株価に連動します。株価が上がれば利益が出ますが、下がれば元本割れの危険があります。短期間での値動きが大きく、リスクが高いです。
- バランス型投資信託
- 株式や債券など複数の資産に分散投資します。リスクは分散されますが、市場全体が不調になると損失が出ます。
- 海外株式型投資信託、新興国株式型投資信託
- 為替リスクや政治リスクも伴うため、値動きが非常に不安定です。
元本割れのリスクを避けるには、リスク許容度に合わせた商品を選びましょう。安定した運用を目指すなら国内債券型投資信託を選ぶべきです。リスクとリターンを天秤にかけながら、慎重に選んでください。
iDeCoで元本割れする理由

iDeCoで元本割れする理由は以下のとおりです。
- 経済状況
- 手数料
経済状況
経済状況の影響により、元本割れのリスクがあります。経済の不安定さや変動が投資商品の価値に影響を与えます。具体的な要因は以下のとおりです。
- インフレ率の上昇
- 金融市場の変動
- 政治的リスクの高まり
- 為替レートの変動
- 金利の変動
インフレ率が上昇すると、物価が上がり、投資商品の価値が下がります。金融市場が不安定になると、株式や債券などの価格が大きく変動します。経済状況の変動は予測が難しいです。
地域経済が停滞すると、地元企業の業績が悪化し、投資商品に影響を与えます。国際貿易の停滞や自然災害、パンデミックの影響も無視できません。経済状況が不安定になると元本割れのリスクが増すため、投資家は慎重な判断が求められます。
手数料
手数料は元本割れに影響を与える主要な要因です。手数料が高いと元本割れのリスクが高いです。手数料はそれぞれ異なるタイミングで発生し、合計すると無視できない額になります。手数料は以下の種類があります。
- 口座管理手数料
- 運用管理手数料
- 加入時の手数料
- 信託報酬
- 解約手数料
金融機関によって手数料の設定が異なるため、手数料の低い金融機関を選ぶことが重要です。
» iDeCoの手数料の種類と節約方法
iDeCoの元本割れを避けるためのポイント

iDeCoの元本割れを避けるためのポイントは以下のとおりです。
- 長期目線で運用する
- リスク許容度に合った商品を選ぶ
- 元本確保型商品を活用する
- 手数料が安い金融機関を選ぶ
長期目線で運用する
短期的な市場の変動に惑わされず、長期目線で運用し、元本割れを避けましょう。市場は短期的には上下しますが、長期的には成長します。過去の市場データを見ると、経済成長と企業の利益増加に合わせて資産が増加しています。
定期的に運用状況を見直し、必要にあわせてリバランスをしましょう。リバランスとは、値上がりした資産を売却し、値下がりした資産を購入し、資産配分を維持することです。リスクを適切に管理できます。毎月一定額をiDeCoに投資し続けることで、高値で購入するリスクを分散し、平均購入価格を下げられます。
老後の生活費や子供の教育費など、具体的な金額と時期を設定してください。目標となる積立額や運用方法が明確になり、モチベーションが高まります。長期目線での運用は基本的な戦略です。短期的な市場の変動に惑わされず、冷静に運用してください。
リスク許容度に合った商品を選ぶ

リスク許容度に合った商品を選びましょう。リスク許容度は投資目標や経済状況に影響します。高リスク・高リターンの商品は元本割れのリスクが高いです。安定性が高い商品は、リターンは少ないものの元本割れのリスクを抑えられ、長期的に安定したリターンを期待できます。安定性が高い商品は以下のとおりです。
- 個人向け国債
- バランス型商品
安定性が高い商品にバランスよく投資すると、リスクを分散できます。株式、債券、預金などを組み合わせてポートフォリオを構築してください。リスク分散とリターンを追求できます。
ファイナンシャルプランナーのアドバイスもおすすめです。金融のプロフェッショナルからの助言で、自己判断では見逃すリスクを察知できます。リスクとリターンのバランスをしっかりと見極め、資産形成しましょう。
» iDeCoの投資信託のラインナップ
元本確保型商品を活用する
元本確保型商品は、iDeCoでの元本割れに非常に有効です。元本を保証するため、元本割れのリスクがほとんどありません。定期預金や保険商品、国債などが元本確保型商品です。元本が保証され、長期的な資産運用で安心して利用できます。
元本確保型商品は、リスクを最小限に抑えたい人や、経済状況に不安を抱える人に適しています。手数料には注意しましょう。
手数料が安い金融機関を選ぶ

手数料が安い金融機関を選びましょう。手数料が高いと資産の成長に影響し、運用成果が悪くなります。金融機関を選ぶポイントは以下のとおりです。
- 預金や管理手数料が無料の金融機関を選ぶ
- 口座開設手数料が低い金融機関を探す
- 信託報酬が低い金融商品のラインナップがあるか確認する
- 比較サイトで複数の金融機関の手数料を調べる
ネット銀行や証券会社は手数料が安く、信託報酬が低い金融商品のラインナップも豊富です。比較サイトを活用して複数の金融機関の手数料を調べてください。最適な金融機関を見つけられます。手数料が安い金融機関で、iDeCoの運用コストを抑えましょう。元本割れのリスクを軽減し、安定した資産運用が可能です。
iDeCoで元本割れが発生したときの対処法

iDeCoで元本割れが発生した場合、冷静な対処が重要になります。ファイナンシャルプランナーや資産運用の専門家にアドバイスを求めることも有効です。具体的な方法を紹介するので参考にしてください。
- 経済状況が落ち着くまで保有する
- 資産配分を変更する
- 分散投資を行う
経済状況が落ち着くまで保有する
経済状況が不安定な時期には慌てて売却せず、経済状況が落ち着くまで待ってください。市場の回復を待つと損失を最小限に抑えられます。経済状況の回復を見極めるために、定期的に市場動向をチェックしましょう。適切なタイミングを判断できます。
経済危機が発生した場合は、多くの投資家が慌てて売却しますが、市場は徐々に回復するため、損失を取り戻せます。一時的な市場の変動に惑わされず、計画的な運用を続けましょう。市場は常に変動しますが、長期的な視点で見れば回復します。
資産配分を変更する

資産配分の変更は、元本割れを避けるために有効です。リスクとリターンのバランスを再評価してください。市場の動向やリスク許容度にあわせて、ポートフォリオの調整が必要です。
ポートフォリオの調整では、安全資産とリスク資産の比率を見直します。市場が不安定な場合は、安全資産の割合を増やすことでリスクを抑えましょう。長期的な成長を期待する場合は、リスク資産の比率を高めることも戦略です。
ポートフォリオは半年から一年に一度は見直しをおすすめします。市場の変動や自分のライフステージの変化に対応するためです。長期的な視点で戦略を再検討し、必要に応じて柔軟に対応することが、成功する資産運用の鍵となります。
分散投資を行う
分散投資は元本割れのリスクを軽減します。集中して投資した資産の価値が下がると、全体の投資が影響を受けるからです。以下のような方法で分散投資が可能です。
- 国内外の株式や債券、不動産などを組み合わせる
- 投資先を複数の国や地域に分散する
- 異なる業種や企業規模の株式を選ぶ
分散投資で一部の投資が損失を出しても、他の投資が利益を上げる可能性が高まります。全体としてのリスクが分散されます。リスクとリターンのバランスの考慮も重要です。リスクの高い資産だけでなく、安全性の高い資産も組み合わせましょう。安定した運用ができます。
iDeCoのよくある質問

iDeCoのよくある以下の質問を解説します。
- iDeCoの途中解約はできる?
- 金融機関が破綻したときはどうなる?
- 加入期間中に死亡したときはどうなる?
- 将来どれくらい年金を受け取れる?
iDeCoの途中解約はできる?
iDeCoは基本的に途中解約ができません。老後に向けた資産形成が目的だからです。原則として60歳になるまで積立金を引き出せません。iDeCoは老後の生活資金の確保が前提であり、急な出費が発生した場合では利用できません。
チェックポイント
万が一の保護として、加入者が死亡した場合や高度障害になった場合には例外的に解約が認められ、積立金を引き出せます。急な出費に備えるためには、iDeCo以外の金融商品や貯蓄との併用がおすすめです。リスクヘッジもできます。
iDeCoは長期的な資産形成に役立つ制度ですが、途中解約ができない点に注意してください。他の資産運用方法とのバランスが重要です。
金融機関が破綻したときはどうなる?

金融機関が破綻した場合でも、預金者の資産は一定の範囲で保護されます。預金保険機構が預金を保護する仕組みがあるため、元本の一定額まで保証を受けられます。安心して資産を預けられる制度です。具体的には以下のとおりです。
- 普通預金や定期預金などの預金商品
- 預金保険機構によって1,000万円までの元本と利息が保証されます。金融機関が破綻しても、預金者は一定額までは資産を守れます。
- 投資信託や株式
- 直接的な元本保証はありません。破綻した金融機関が扱う運用資産は、他の金融機関に移管されます。投資信託の場合は新しい運用会社が引き継ぎ運用するので安心です。
金融機関破綻時には、預金者に詳細な情報提供と対応指示が行われます。情報提供に注視し、適切な対応を取ることで、混乱を最小限に抑えましょう。
加入期間中に死亡したときはどうなる?
加入期間中に死亡した場合、加入者の掛金に応じた金額が遺族に支払われます。遺族給付金として、一時金または年金として受け取れます。具体的には以下のとおりです。
- 遺族給付金の額は、死亡時点の運用残高に基づく
- 受取人は、法定相続人か、あらかじめ指定された受取人になる
- 遺族給付金の受け取りには、所得税および住民税がかかる
- 受取手続きを行うためには、証明書類や請求書の提出が必要になる
突然の不幸に見舞われた際でも、遺族の生活を支える助けとなります。安心してiDeCoを活用してください。
将来どれくらい年金を受け取れる?

年金の受取額は、加入期間、掛金額、運用利回りによって異なります。長期的に運用を行うことで、複利効果が期待でき、受取額が増加します。
チェックポイント
具体的な受取額を確認する方法は、日本年金機構が提供する「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」です。受取時には一時金として一括で受け取るか、年金として分割で受け取るかを選択できます。ライフスタイルに合わせて選びましょう。
iDeCoの運用成績によっては、元本割れに注意が必要です。計画的に運用し、定期的に運用状況を確認してください。
» iDeCoは何歳から始められるかを解説
まとめ

iDeCoは、老後の資産形成に役立つ制度です。税制優遇が受けられ、月々の拠出金が税控除の対象になります。運用次第で資産が増えます。
元本割れのリスクや手数料の負担があるため、リスク管理をしましょう。長期目線での運用やリスクに合った商品選び、手数料が安い金融機関の選定が元本割れを避けるポイントです。
元本割れが発生した場合は、経済状況の回復を待ってください。資産配分を見直すなどの対策が必要です。iDeCoは途中解約ができないものの、金融機関が破綻した場合や加入者が死亡した場合には保護制度が適用されます。iDeCoは、賢く運用することで将来の年金受取額を増やせます。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説