PR

フリーランスになって、老後の資金準備に不安を感じる人は多くいます。iDeCoと小規模企業共済は、フリーランスも利用できる制度です。会社員時代の年金や退職金制度がなくなり不安な人も、老後に備えられます。この記事では、iDeCoと小規模企業共済の詳細や違いを詳しく解説します。
記事を読めば、それぞれの制度の特徴や違いがわかり、自分に合った老後の資金準備方法を選択できるため必見です。iDeCoは運用次第で高い収益が期待でき、小規模企業共済は安全性が高い制度です。それぞれのメリットや注意点を理解し、必要に応じて併用しましょう。
iDeCo(確定拠出年金)とは私的年金制度の一つ
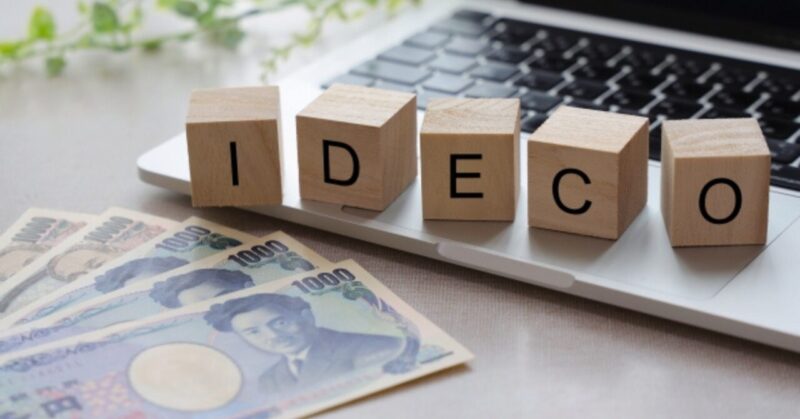
iDeCoに関する、以下の3点を解説します。
- iDeCoの加入対象者
- iDeCoのメリット
- iDeCoの注意点
iDeCoの加入対象者
iDeCoの加入対象者は幅広いのが特徴です。60歳未満の日本国内に住む人であれば、職業や雇用形態に関わらず加入できます。加入対象者は以下のとおりです。
- 会社員
- 公務員
- 自営業者
- 専業主婦・主夫
- 学生
- パート・アルバイト
確定給付型年金のみに加入している会社員も対象です。企業型確定拠出年金に加入している人でも、会社がiDeCoへの加入を認めている場合は利用できます。iDeCoは年齢制限があるため注意が必要です。60歳以上の人は新規加入できません。
国民年金の第3号被保険者(専業主婦や主夫など)は、2018年以降に加入できるようになりました。iDeCoは幅広い層をカバーする年金制度です。自分が対象者かを確認し、将来の資産形成に役立てましょう。
iDeCoのメリット

iDeCoのメリットは税制優遇を受けられる点です。掛金全額が所得控除の対象で、運用益が非課税になるのが魅力です。受け取り時も税制優遇が受けられます。iDeCoの優遇措置により、効率的に資産形成を行えます。iDeCoでは自分で運用商品を選択できるため、投資スタイルに合わせた資産運用が可能です。
60歳から受け取りが始まり、老後の資金として活用できるのも魅力です。転職や退職時には他の年金制度からの移管ができるため、柔軟な対応ができます。万が一の場合も、遺族に一時金として支払われるので安心です。個人事業主は、掛金を必要経費として計上できるのもメリットです。
金融機関の倒産リスクからも保護されているため、安全性も高い制度と言えます。
» 退職後のiDeCoの運用方法と手続きの仕方、金融機関の選び方
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
iDeCoの注意点
iDeCoは掛金を60歳まで引き出せないため注意が必要です。iDeCoは長期的な資産形成のための制度で、原則として60歳になるまで掛金を引き出せません。急に資金が必要になった場合でも、利用できない制約があるのがデメリットです。運用次第で元本割れのリスクもあります。
自分で運用商品を選択し、資産配分を決める必要があるため、投資の知識や経験が必要です。他にも以下の制限やデメリットがあります。
- 年間の拠出限度額
- 掛金の変更や中断の制限
- 解約時のペナルティ
- 受け取り時の課税
- 他の年金制度との併用制限
- 運用手数料
注意点を十分に理解したうえで、自分の状況に合っているかを慎重に検討しましょう。長期的な視点で資産形成を行う余裕がある場合、iDeCoは有効な選択肢です。
» iDeCoが元本割れする原因と対処法
小規模企業共済とは中小企業の経営者や個人事業主向けの退職金制度

小規模企業共済に関する、以下の3点を解説します。
- 小規模企業共済の加入対象者
- 小規模企業共済のメリット
- 小規模企業共済の注意点
小規模企業共済の加入対象者
小規模企業共済の加入対象者は、以下のとおりです。
- 従業員20人以下の個人事業主
- 従業員20人以下の会社の役員
- 小規模企業者の組合の役員
- 従業員20人以下の企業組合の組合員
- 従業員20人以下の協業組合の組合員
業種によって、従業員数の条件が異なる場合があります。商業やサービス業では、従業員が5人以下の事業主が対象です。特定の専門職も加入できます。弁護士や税理士、公認会計士などの士業者で、従業員が5人以下の事業を営む人も対象です。
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主を支援するための制度です。自営業や小さな会社の役員にも適しています。
小規模企業共済のメリット
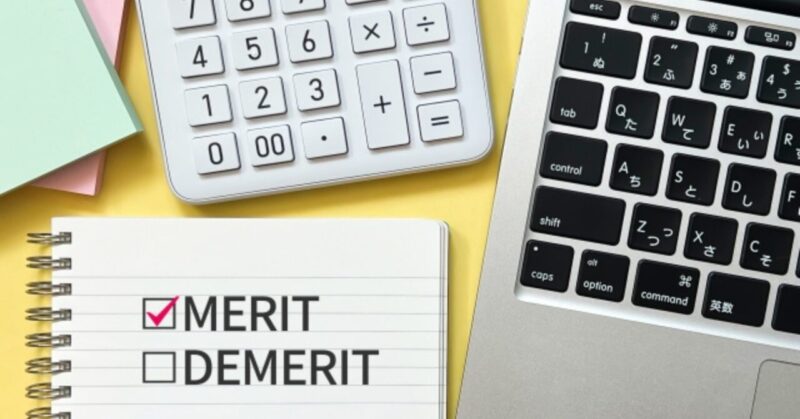
小規模企業共済のメリットは、税制優遇と柔軟な資金運用ができる点です。掛金が全額所得控除の対象となり、受け取る共済金の半額が、退職所得控除の対象となります。共済金は一時金または分割で受け取れ、事業資金の貸付制度も利用できます。掛金は、月額1,000~70,000円まで自由に設定可能です。
小規模企業共済では掛金の増額が可能で、前納制度も利用できます。契約者貸付制度があり、急な資金需要にも対応可能です。共済金は非課税で受け取れるうえ、掛金は預金保険制度の対象となるため安心です。掛金の積み立ても自動引き落としで手間なく行えます。健康診断なしで加入でき、手続きも簡単です。
小規模企業共済の注意点
小規模企業共済は、掛金の上限が月額70,000円と固定されているため、柔軟な資金運用ができません。解約時には、支払われる解約手当金に対して高率の課税があるため注意が必要です。運用益が期待できず、インフレリスクもあります。加入後の掛金増額は可能ですが、減額は原則できません。
65歳までに退職しないと、受給を開始できないため注意しましょう。共済金の受け取り方法の変更も、原則として認められていません。個人事業主が法人化した場合、資格を喪失します。経営状況が悪化しても、掛金の支払いは継続しなければなりません。加入期間が短いと、受け取る共済金が少なくなる可能性があります。
一時金で受け取る場合は、退職所得控除が適用されないため要注意です。自分の経営状況や将来の計画に合わせて、慎重に判断しましょう。
iDeCoと小規模企業共済の違い

iDeCoと小規模企業共済の違いを、以下の8点に分けて解説します。
- 所得控除
- 受け取り方法
- 加入資格
- 掛金
- 手数料
- 貸付制度
- 解約条件
- 元本割れの可能性
所得控除
iDeCoと小規模企業共済を利用すると、税金の負担を軽くできます。iDeCoの場合、支払った掛金の全額が所得控除の対象となり、年間の上限は40万円です。小規模企業共済は掛金の一部が所得控除の対象となり、上限は年間70万円です。
iDeCoと小規模企業共済はどちらも所得控除の対象となりますが、小規模企業共済は事業税の軽減効果も期待できます。iDeCoと小規模企業共済を併用すると、最大で110万円の所得控除が可能です。所得控除により課税所得が減るため、税負担が軽くなります。
所得控除の効果は加入者の所得税率によって変わります。高い所得の人ほど、所得控除による恩恵が大きくなるのが特徴です。所得控除は、掛金を支払った時点で適用されます。早めに加入して掛金を支払うと、加入した年の税金を軽減できるためおすすめです。
受け取り方法

iDeCoは、一時金や年金で受け取れます。一時金と年金を組み合わせて受け取ることも可能です。年金として受け取る場合は、5年以上20年以内の期間から選択できます。小規模企業共済の受け取り方法は、一時金または分割での受け取りが選択可能です。
iDeCoは60歳から受け取りを開始できます。小規模企業共済は、65歳までに契約解除すると受け取れます。iDeCoは受け取り方法を途中で変更できますが、小規模企業共済は一時金を選んだ場合、分割への変更はできません。
受け取り方法の選択は、将来の生活設計に大きく影響するため、自分のニーズに合った方法を選びましょう。
加入資格
iDeCoは、60歳未満の国民年金加入者が対象です。小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が対象です。iDeCoには年齢制限がありますが、小規模企業共済にはありません。職業によって加入資格が変わります。iDeCoは公務員や会社員も加入できます。
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が主な対象です。iDeCoは国民年金基金加入者も対象です。小規模企業共済には事業規模や従業員数に制限があります。共同経営者も加入できるなど、柔軟な面もあります。
掛金

iDeCoの掛金は月額68,000円まで、小規模企業共済は月額70,000円までです。iDeCoの掛金は、加入者の年齢や職業によって上限額が異なります。小規模企業共済は1,000円単位で設定できるため、より細かな調整が可能です。iDeCoでは加入者が自由に運用方法を選択できるのが特徴です。
小規模企業共済は固定金利で運用されるため、運用方法の選択肢はありません。iDeCoは掛金の変更が可能ですが、小規模企業共済は掛金の減額ができません。iDeCoと小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象となるため、税制面でのメリットがあります。
掛金納付期間はiDeCoが60歳まで、小規模企業共済は65歳までです。
手数料
iDeCoは運用商品によって手数料が変わり、口座管理手数料が月額数百円かかります。運用商品の売買手数料や信託報酬が発生する場合もあります。小規模企業共済は原則として手数料がかかりません。掛金以外の費用負担がほとんどないため、安心して利用できます。手数料の面では、小規模企業共済の方が優位です。
» iDeCoの手数料の種類と節約方法
貸付制度
iDeCoには貸付制度がありませんが、小規模企業共済には契約者貸付制度があります。小規模企業共済は、納付した掛金の範囲内で貸付を受けられ、年利1.5%(2023年4月現在)の低金利で借りられます。貸付期間は最長5年間で、事業資金や事業承継資金として利用可能です。
小規模企業共済の貸付制度は、担保や保証人が不要で、原則として即日融資を受けられます。繰り上げ返済が可能で、手数料がかからないのがメリットです。iDeCoには貸付制度がないため、急な資金需要に対応できません。小規模企業共済は、事業の運営や拡大に必要な資金を、柔軟に調達できる仕組みを提供しています。
解約条件
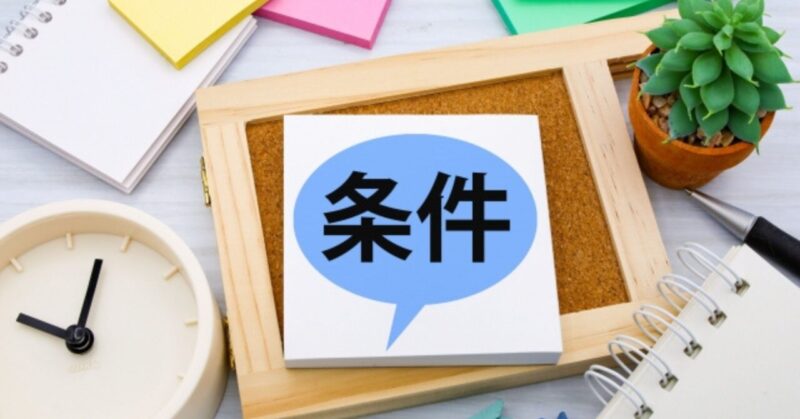
iDeCoは原則60歳まで中途解約できませんが、小規模企業共済は任意の時期に解約可能です。iDeCoの場合、死亡時や重度障害時といった例外的な状況でのみ中途解約が認められます。小規模企業共済は解約時に、解約手当金が支払われます。解約手当金は、一時所得として課税されるため注意が必要です。
iDeCoを解約すると、積み立ててきた分の税制優遇が取り消されるため注意しましょう。転職や退職時には他の年金制度へ移換できるため、柔軟な対応が可能です。小規模企業共済は解約後も再加入できるため、一時的な資金需要に対応しやすい制度です。
» iDeCoは途中解約できない?難しい理由と解約ができるケース
» 転職時のiDeCoはどうする?iDeCoのスムーズな管理方法
元本割れの可能性
iDeCoは運用次第で元本割れの可能性があります。小規模企業共済は元本が保証されているのが特徴です。iDeCoの場合、自己責任での運用が求められます。リスクとリターンのバランスを調整できますが、市場の変動に影響を受けやすいため、慎重な運用が必要です。
小規模企業共済は安全性が高く、元本割れのリスクがない分、運用利回りは低めになる傾向があります。予定利率が低下傾向にあるものの、元本は確実に確保されるため、安定性を重視する人におすすめです。リスク許容度や目的に応じて、適切に選択しましょう。
iDeCoと小規模企業共済は併用できる

iDeCoと小規模企業共済は同時加入が可能で、税制優遇を最大限に活用できるのがメリットです。iDeCoと小規模企業共済の併用に関する、以下の2点を解説します。
- 併用するメリット
- 併用するときのポイント
併用するメリット
iDeCoと小規模企業共済を併用すると、税制優遇の効果が大きくなり、所得控除の枠が広がります。税金面での恩恵が大きくなるのがメリットです。リスクの分散も可能です。iDeCoと小規模企業共済を併用すれば、ライフプランに合わせた柔軟な資金計画が立てやすくなります。
将来の不確実性に対するセーフティネットが強化されるため、安心して老後に備えられます。
併用するときのポイント
iDeCoと小規模企業共済を併用する際は、自分の収入や資産状況を考慮して、適切な掛金を設定しましょう。特徴を理解し、長期的な資産形成を計画することが重要です。税制優遇の上限を把握し、最大限活用するのもポイントです。リスク分散を意識して、運用商品を選択しましょう。
定期的に運用状況を確認し、必要に応じて見直すのも大切です。将来の受け取り方法や時期も検討しましょう。加入資格の変更に注意し、適宜見直しを行うのも重要です。専門家のアドバイスを受けると、より効果的な資金計画が立てられます。
まとめ
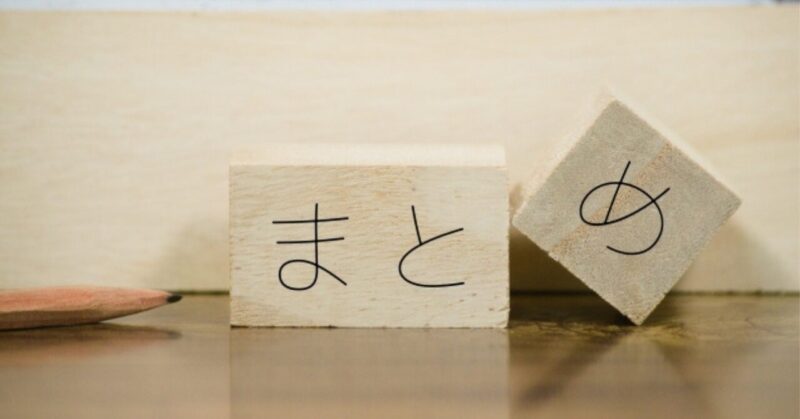
iDeCoと小規模企業共済を併用すると、老後資金をより充実させられます。iDeCoは私的年金制度として、運用次第で高い収益が期待できるのが特徴です。小規模企業共済は、退職金制度として元本が保証されています。
税制優遇や受け取り方法、加入資格など、それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合わせた組み合わせを選びましょう。iDeCoと小規模企業共済を上手に活用して、老後の生活に備えてください。