PR
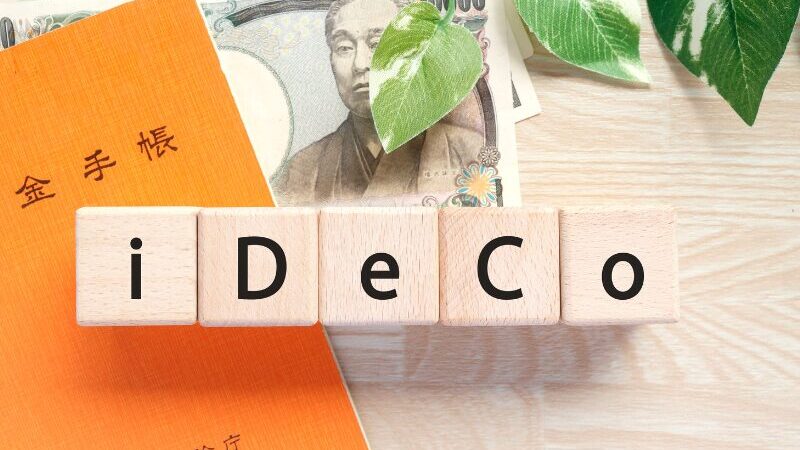
「将来のためにiDeCo(確定拠出年金)を始めたいけど、節税効果がどれくらいあるのかわからない…」と悩んでいませんか?自営業やフリーランスは特に、定年したら国民年金に頼るしかないため、老後資産に不安を感じている人も多くいます。
iDeCoは老後の資産形成を支援する制度であり、節税効果も高いのが特徴です。この記事では、iDeCoの仕組みから節税メリット、具体的な節税シミュレーションまで詳しく解説します。最後まで読めば、自分に合った拠出額を設定して、節税効果を最大限に引き出す方法がわかります。
iDeCoの加入条件や運用方法を理解し、老後の資産形成に役立てましょう。
iDeCoとは老後資金を増やす年金制度

iDeCoは個人型確定拠出年金の略称で、自分で拠出額を決め、運用先を選ぶ年金制度です。老後の資産形成に役立つiDeCoの以下2点について詳しく解説します。
- iDeCoの仕組みと運用方法
- iDeCoの加入条件と対象者
iDeCoの仕組みと運用方法
iDeCoは、老後の資産形成に役立つ制度です。資産運用することで年金資金を積み立てます。iDeCoは、20歳以上65歳未満で、日本国内で勤務・居住している方であれば誰でも加入できます。しかし、職業によって拠出できる限度額が異なるため、確認が必要です。
iDeCoは金融機関を通して加入申し込みをします。資産運用するために口座の開設が必要です。iDeCoでは主に以下の金融商品を購入できます。
- 元本確保型商品(定期預金)
- 投資信託
運用中は自由に掛金の増減や運用商品の変更が可能ですが、積み立てた資産は、60歳以上にならないと受け取れません。受取時には一時金で受け取る方法と、年金形式で分割して受け取る方法があります。一時金と年金形式での方法を組み合わせて受け取ることも可能です。
iDeCoで積み立てた掛金は所得税控除の対象となるので、始めた年から節税効果を実感できます。iDeCoで運用した場合、運用益がすべて非課税となるのも魅力的なポイントです。iDeCoの仕組みと運用方法を理解することで、老後の資産形成を効果的に進められます。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
iDeCoの加入条件と対象者
iDeCoに加入条件は以下の2つです。
- 国民年金保険料を納付していること
- 20歳以上60歳未満であること
iDeCoは、国民年金を納付している第1号被保険者や第2号被保険者、第3号被保険者が対象となります。
| 加入区分 | 対象者 |
| 第1号被保険者 | 自営業者とその家族、フリーランス、学生など |
| 第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者(会社員や公務員など) |
| 第3号被保険者 | 厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者 |
| 国民年金の任意加入被保険者 | 国民年金に加入した方 |
ほぼすべての日本国内に住む幅広い職業やライフスタイルの方々が加入可能です。専業主婦(主夫)であっても加入できるので、将来のために積極的に活用できます。ただし、海外に居住している場合、iDeCoに加入できないので注意してください。
iDeCoの3つの節税メリット

iDeCoには以下3つの節税メリットがあります。
- 掛金が全額所得控除になる
- 運用益が非課税になる
- 受取時に税制優遇を受けられる
掛金が全額所得控除になる
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象になるため、所得税や住民税の負担が軽減されます。所得税率は年収によって変動するので、下記の表をご参照ください。
| 課税所得金額 | 所得税率 |
| 195万円未満 | 5% |
| 195〜329万9,000円 | 10% |
| 330〜694万9,000円 | 20% |
| 695〜899万9,000円 | 23% |
| 900〜1,799万9,000円 | 33% |
| 1,800〜3,999万9,000円 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
年収450万円の会社員が年間24万円の掛金を拠出した場合、所得税率が20%なので、約4万8千円の節税効果を受けられます。年収が高い人ほど所得税率が上がるので、iDeCoの節税効果が大きくなります。所得控除を受けるには、年末調整もしくは、確定申告時に申請する必要があるので、忘れないようにしましょう。
運用益が非課税になる

通常、金融商品の利益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoでの運用益はすべて免除されます。iDeCoで運用した投資信託や株式で得た利益は税金を払う必要がないので、老後の資産形成に優位に働きます。ただし、iDeCoは受け取る方法によって利用できる税制優遇の制度が異なるので注意が必要です。
受取時に税制優遇を受けられる
iDeCoの受取時には、以下の3つ方法があります。
- 年金形式
- 一時金
- 年金形式と一時金の組み合わせ
受け取り方法によって利用できる税制優遇は以下のとおりです。
| 受取方法 | 税制優遇 |
| 年金方式 | 公的年金等控除の対象 |
| 一時金 | 退職所得控除の対象 |
「公的年金等控除」は受取額に応じて控除額が変わり、年金の受取額が多いほど控除額も増えます。「退職所得控除」は勤続年数に応じて一定額が控除されるため、勤続年数が長い人に有利です。iDeCoの節税メリットを生かすためにも、どの受け取り方法が自分に適しているか検討しましょう。
iDeCoの拠出限度額
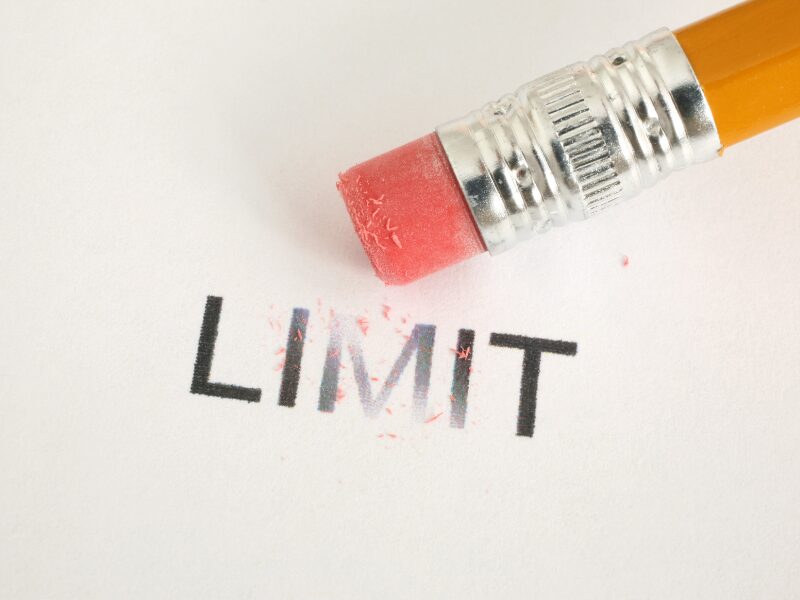
iDeCoの拠出限度額は、各職業の利用できる年金制度に応じて設定されています。職業別の拠出限度額と自分に合った拠出額の設定方法について解説します。
職業別の拠出限度額一覧
iDeCoの拠出限度額は職業によって異なり、具体的な拠出限度額は以下のとおりです。
| 職業 | 拠出限度額(月額) | 拠出限度額(年間) |
| 自営業者 | 68,000円 | 816,000円 |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 276,000円 |
| 会社員(企業年金あり) | 12,000円 | 144,000円 |
| 公務員(共済組合員) | 12,000円 | 144,000円 |
| 専業主婦(主夫) | 23,000円 | 276,000円 |
会社員よりも自営業者の拠出限度額が大きいのは、定年後に受け取れる年金が国民年金のみだからです。一方、会社員は厚生年金に加入できるため、自営業者と比較すると、受け取れる年金額が高額になります。iDeCoは老後に向けた資産形成を支援するための制度です。
厚生年金に加入できない自営業者や専業主婦(主夫)に優しい仕組みになっています。
自分に合った拠出額の設定方法
iDeCoの拠出額は、個人の収支状況と将来設計にもとづいて検討しましょう。拠出額を決める際に考慮すべき要素は以下のとおりです。
- 現在の収支分析:毎月の余剰資金を把握
- 将来設計の考慮:教育費や住宅購入などの大きな支出を予測
- 老後資金の試算:現役時代の収入の約70%を目安に計算
無理のない範囲で拠出額を設定するには、現在の収入と支出を見直し、毎月の余剰資金を把握することが大切です。iDeCoは長期間資産が拘束され、途中で解約できません。教育費や住宅購入など支出が予想される場合、別に資金を確保する必要があります。
毎月の掛金は無理なく継続できる金額に設定し、定期的に見直すことも大切です。
iDeCoの節税効果を最大限に引き出す方法

iDeCoの節税効果を最大限に引き出すためには、以下2つのポイントがあります。
- 拠出限度額を長期間運用する
- 他の税制優遇制度と併用する
拠出限度額を長期間運用することで、所得控除の恩恵を最大限に受けられます。他の税制優遇制度と併用することも大切です。
拠出限度額を長期間運用する
iDeCoの税制優遇を最大限に活用するためには、拠出上限額を長期運用することが重要です。iDeCoでは掛金が全額所得控除されるため、掛金を拠出限度額に設定することで節税効果が最大化されます。運用期間が長いほど非課税総額が増え、所得が高い人ほど、所得控除によるの節税効果が大きくなります。
iDeCoによる税制優遇を最大限に引き出すために、早い段階でiDeCoに加入し、運用期間を長く確保しましょう。ただし、日々の幸福度を下げないように、無理のない金額を毎月積み立てることが大切です。
他の税制優遇制度と併用する
iDeCo の節税効果を最大化するには、他の税制優遇制度との併用が効果的です。複数の税制優遇制度を利用することで、節税効果を最大限活用し、より効率的な資産形成ができます。iDeCoと相性の良い税制優遇制度は以下の2つです。
- 新NISA
- ふるさと納税
iDeCoの掛け金は上限額が決まっているため、より高額な資金を運用したい場合は、新NISAがおすすめです。新NISAは年間360万まで非課税で運用できます。ふるさと納税は節税効果に加えて、返礼品がもらえるので、寄付しながら特産品を楽しめるのが魅力です。
他の税制優遇制度と併用して税負担を軽減し、資産形成を効率的に進めましょう。
【職業別】iDeCoの節税額のシミュレーション

iDeCoを利用することで、どのくらい節税効果が得られるのか、職業別でシミュレーションしてみました。今回、シミュレーションした職業は以下のとおりです。
- 会社員
- 自営業者
- 公務員
- 専業主婦(主夫)
会社員
会社員の場合、拠出限度額は月額23,000円までなので、年間最大276,000円の掛金が全額所得控除対象となります。職場の企業型DCと併用すると、個人で掛けられる拠出限度額が年間最大144,000円までなので注意しましょう。会社員のiDeCo利用による所得税の節税効果は以下のとおりです。
| 年収 | 所得税率 | 節税効果(企業型DCなし) | 節税効果(企業型DCあり) |
| 150万円以下 | 5% | 年間13,800円 | 年間7,200円 |
| 150万円超~330万円以下 | 10% | 年間27,600円 | 年間14,400円 |
| 330万円超~650万円以下 | 20% | 年間55,200円 | 年間28,800円 |
| 650万円超~1,000万円以下 | 23% | 年間63,480円 | 年間33,120円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 30% | 年間82,800円 | 年間43,200円 |
年収500万円の会社員がiDeCoを最大限に活用した場合、所得税だけでも年間55,200円の節税効果が得られます。住民税まで加味すると節税効果は約7~10万円程度になります。勤続年数が長い会社員であれば、節税効果を最大限に活かすために、一時金として受け取る方法がおすすめです。
自営業者
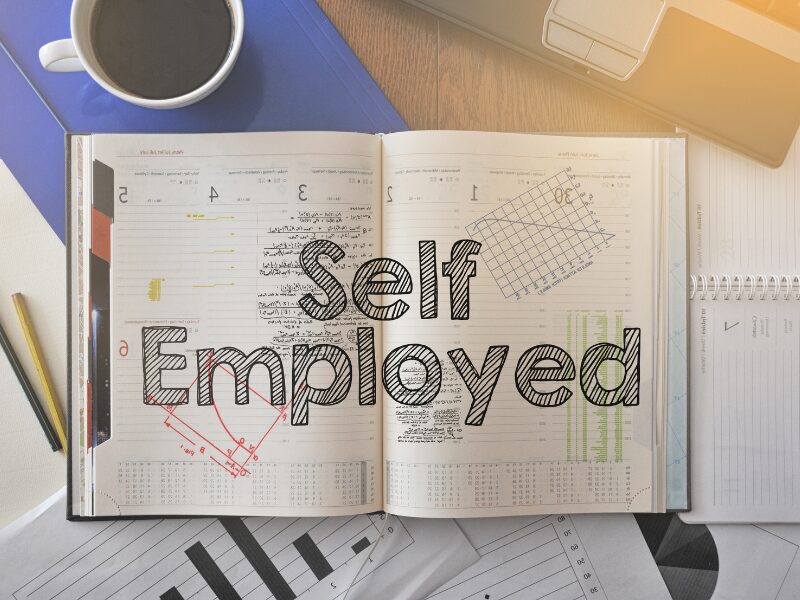
自営業者は国民年金の第1号被保険者に該当します。iDeCoへの最大の掛金は月額68,000円までとなり、全額所得控除の対象となります。年間最大816,000円の所得控除が受けられるので、他の職業よりも節税効果が高いのが特徴です。自営業者がiDeCoを活用することによる、所得税の節税効果は以下のとおりです。
| 年収 | 所得税率 | 節税効果 |
| 150万円以下 | 5% | 年間40,800円 |
| 150万円超~330万円以下 | 10% | 年間81,600円 |
| 330万円超~650万円以下 | 20% | 年間163,200円 |
| 650万円超~1,000万円以下 | 23% | 年間187,680円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 30% | 年間244,800円 |
年収800万円の自営業者の場合、所得税だけでも年間の節税効果は最大187,680円に達します。住民税まで加味すると節税効果は約20~30万円程度になります。自営業者にとってiDeCoは、大きな節税効果と効率的な資産形成を両立できる有効な手段です。
無理のない範囲で運用することで、将来の安定した資金確保につながります。自身の事業状況とライフプランに合わせて、iDeCoを効果的に活用しましょう。
公務員
公務員の場合、iDeCoの掛金は月額最大12,000円で、年間最大144,000円の所得控除が受けられます。iDeCoによる所得税の節税効果は以下のとおりです。
| 年収 | 所得税率 | 節税効果 |
| 150万円超~330万円以下 | 10% | 年間14,400円 |
| 330万円超~650万円以下 | 20% | 年間28,800円 |
| 650万円超~1,000万円以下 | 23% | 年間33,120円 |
他の職業に比べて控除額は少ないですが、節税効果は無視できません。年収500万円の公務員が最大限にiDeCoを利用した場合、所得税だけでも年間28,800の節税効果があります。公務員は、60歳で定年が来ることや、掛け金が他の職業よりも少ないので、早期からiDeCoを始めるのが重要です。
早期に加入することで、運用期間を確保し、老後資金の効率的な準備ができます。
専業主婦(主夫)

国民年金の第3号被保険者である専業主婦(主夫)もiDeCoを利用することで節税が可能です。月額最大23,000円の掛金が全額所得控除対象となり、年間最大276,000円の所得控除が受けられます。資産運用による利益額は非課税になるので、専業主婦(主夫)でもiDeCoで老後の資産形成を優位に進めれらます。
ただし、専業主婦(主夫)は所得がないため所得税の大きな節税効果は期待できません。専業主婦(主夫)の場合、運用益が非課税になる点に魅力を感じられれば、iDeCoを利用すると良いでしょう。専業主婦(主夫)でもiDeCoを利用することで、老後資金を備える一助となるため、経済的な安心を得られます。
まとめ

iDeCoは効果的な節税と資産形成を組み合わせて老後の資産形成を支援してくれる制度です。iDeCoの節税効果として以下の3つが挙げられます。
- 掛金が全額所得控除される
- 運用益が非課税になる
- 受け取り時に税制優遇措置がある
ただし、掛金の上限額は職業によって異なるので注意が必要です。iDeCoは金融商品を買った時点で、掛金を全額所得控除できる節税効果に優れた制度です。ただし、節税効果を最大限に引き出すには適切な受け取り方を知っておく必要があります。
会社に長く勤めていた人は一時金として、年収が高い人は年金として受け取ることで節税効果を最大限に引き出せます。老後の資産形成を効率的に進めるために、自分に合った拠出額を設定し、他の税制優遇制度と併用することも大切です。