PR

老後資金を準備したいけど、老後までに間に合うのかを不安に感じる方は多いです。フリーランスだと、会社員に比べもらえる年金が少ないため、より不安を感じてしまいます。老後資金の準備には、iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用がおすすめです。iDeCoは自分で運用できる、老後資金の準備に役立つ年金です。
この記事では、iDeCoの基本的な仕組みや50代以降からiDeCoを始める際の注意点を解説します。記事を読むと、iDeCoを始めるべき理由と、効率的に老後資金を準備する方法がわかります。老後に向けた資金計画を立て、自分に合った方法で安心した老後を迎えられるように準備してください。
iDeCoとは個人で運用を行う公的年金制度
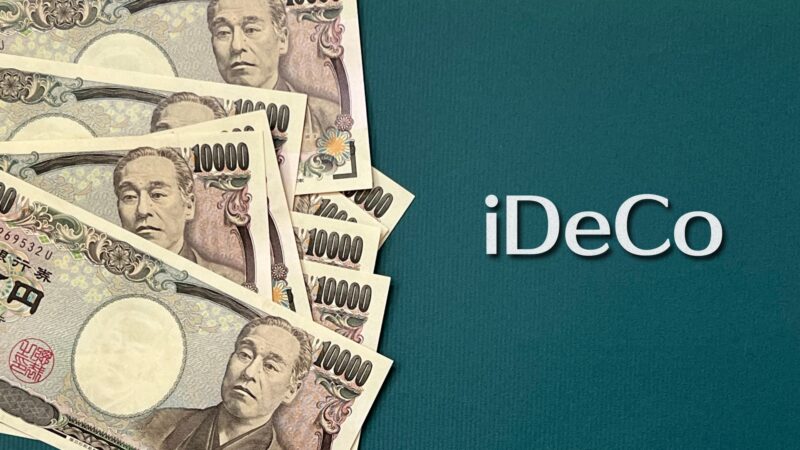
iDeCoは公的年金制度の一つです。自分で拠出金を積立てて、将来的に税制優遇を受けながら年金として受け取れます。積立時や運用時、受取時に税金が軽減されるので、節税効果が得られます。投資信託や定期預金などの商品を自分で選択して運用し、成果に応じて将来の年金額が決まる制度です。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
iDeCoのメリット
iDeCoの主なメリットを下記にまとめました。
- 所得控除を受けられる
- 運用益が非課税である
- 退職所得控除を適用できる
- 運用商品を自分で選択できる
- 老後の資産形成に役立つ
- 節税効果が高い
- 定期的に運用商品の見直しができる
選択肢が豊富で、節税効果も期待できる点が大きなメリットです。
» iDeCoのメリット・デメリットを徹底解説!
iDeCoは何歳まで加入できるのか

iDeCoに加入できる年齢は基本的に20歳以上60歳未満です。ただし、2022年5月の法改正により、60歳以上65歳未満の方も一部iDeCoに加入できるようになりました。
2022年5月の法改正での変更点
2022年5月の法改正により、iDeCoの制度が変更されました。主な変更点を下記にまとめたので参考にしてください。
- 加入可能年齢が65歳まで延長
- 企業型確定拠出年金と併用可能
- 受給開始年齢が最大75歳まで延長
- 中小企業従業員も加入対象
法改正により、加入年齢の広がりや加入対象者の拡大が行われました。
iDeCoは何歳から受け取れるのか
iDeCoの受給開始年齢は60歳からが基本ですが、加入期間によって変動します。加入期間が10年以上ある場合は、60歳から受給可能です。加入期間が10年未満の場合、受給開始年齢が遅くなり、最大で75歳から受給開始します。
60歳から受け取る場合と75歳から受け取る場合では、75歳から受け取る方が受給額が高くなる可能性があります。受給開始を遅らせることで、運用期間が長くなり、資産が増える場合があるからです。受給開始年齢を選ぶ際には、自分のライフプランや経済状況を考慮した上で決定しましょう。
50代・60代からでもiDeCoを始めるべき理由

50代や60代からでもiDeCoを始めるべき理由はいくつかあります。主な理由を下記にまとめました。
- 老後資金の足しになる
- 所得税・住民税の節税ができる
- 退職金の節税ができる
50代や60代からでもiDeCoの活用おすすめです。iDeCoは老後の生活を安定させるための、効果的な方法の一つです。
老後資金の足しになる
iDeCoは定期的に拠出をし、自分で資金を積み立てていくため、老後資金の足しになります。運用益が非課税なので、効率的に資金を増やせます。公的年金だけでは不足すると感じる方も多いですが、iDeCoの利用により、自分で老後資金の準備が可能です。
毎月一定額を積み立てることで、長期的にまとまった資金を形成できる点がiDeCoの大きな魅力です。運用益が非課税なので、他の投資方法と比べてもお得に資金を増やせます。節税効果も得られるため、老後資金の効率的な準備が可能です。
iDeCoによる拠出金は全額所得控除の対象なので、所得税や住民税の負担を軽減できます。節税により手元に残るお金が増え、追加で積み立てることも可能です。iDeCoの活用により、公的年金に加え、自分で老後の資金を確保できます。長期的な視点で積み立てることにより、将来の不安が減り、豊かな老後生活につながります。
所得税・住民税の節税ができる

iDeCoでの運用により、所得税と住民税の節税が可能です。iDeCoの掛金は、全額所得控除の対象です。節税効果は、所得控除により課税所得が減少するため得られます。iDeCoの掛金を毎月1万円拠出する場合、年間で12万円が所得から控除され、所得税だけでなく住民税の負担も軽減されます。
住民税は年収に応じて課税されるため、控除額が多いほど節税効果は大きいです。iDeCoは年収が高い方にとって、有効な節税方法の一つです。節税効果を最大限に活用するためには、適切な掛金額を設定し、長期間にわたる拠出の継続が欠かせません。
退職金の節税ができる
iDeCoでは、退職金控除を適用できるので節税効果が得られます。iDeCoを受給する際、退職所得として扱われるので、所得税や住民税が低くなります。受給時に複数年に分けて受け取ることで、税負担の分散が可能です。iDeCoの活用は、退職金の節税につながるので、おすすめです。
50代以降でiDeCoに加入するときの注意点

50代以降でiDeCoに加入する際には、いくつか注意点があります。主な注意点を下記にまとめました。
- 加入期間が短い
- 運用期間が短い
- 受給開始年齢に制限がある
考えられる注意点やリスク、自分の状況を考慮した上で、加入を検討してください。
加入期間が短い
50代以降からiDeCoを始める場合、加入期間が短くなるので注意が必要です。加入期間が短いと、老後の資金形成においてデメリットが生じます。主なデメリットの一つは、積立金額を増やすための時間が限定的であることです。
20〜30代からiDeCoに加入すると、長い年月をかけて積み立てられますが、50〜60代からだと積立期間が短くなります。30年の運用期間と10年の運用期間では、同じ金額を積み立てても得られるリターンに差が生じやすいです。50代以降はリスク許容度が低い傾向にあるので、投資のリスクを取りづらくなります。
リスク許容度が低い場合、ハイリスク・ハイリターンの商品への投資には注意が必要です。
運用期間が短い

運用期間の短さは、いくつかのデメリットにつながります。主なデメリットを下記にまとめました。
- 手数料の割合が大きくなりやすい
- 分散投資が難しい
- 計画的な資産形成が難しい
- 資産が十分に成長しない可能性がある
運用期間が短い場合は、適切な投資戦略が必要です。事前に投資について学んでから検討しましょう。
受給開始年齢に制限がある
iDeCoの受給開始年齢には制限があるので、50代以降から始める場合は注意が必要です。原則として、受給開始は60歳からとなっていますが、加入期間が10年未満の場合は受給開始年齢が遅れます。加入期間が10年未満の場合の受給開始年齢を下記にまとめました。
- 加入期間が8年以上10年未満の場合の受給開始年齢:61歳
- 加入期間が6年以上8年未満の場合の受給開始年齢:62歳
- 加入期間が4年以上6年未満の場合の受給開始年齢:63歳
- 加入期間が2年以上4年未満の場合の受給開始年齢:64歳
- 加入期間が1ヶ月以上2年未満の場合の受給開始年齢:65歳
加入期間が短い場合、受給開始年齢が遅れる点に注意が必要です。加入期間が長ければ長いほど、早く受給を開始できます。受給開始年齢に関する情報を考慮して、加入や運用の計画を立ててください。
iDeCoの申込み手続きの流れ

iDeCoの申込み手続きの手順を下記にまとめました。
- 運用機関の選定
- 申請書類の取り寄せ
- 書類の記入
- 運用機関への書類提出
- 運用商品の選択
運用機関の選定
iDeCoを申込む際、始めに運用機関を選定してください。取扱商品が異なるので、運用機関の選択は大切です。証券会社や金融機関など、さまざまな機関で取り扱いをしているので、比較して選定してください。運用機関を選定したあとは、書類を取り寄せましょう。主な取り寄せ方法は下記のとおりです。
- iDeCoの公式サイトから資料請求
- 各金融機関のiDeCo専用ページから資料請求
- 郵送での書類取り寄せ
- オンラインでの書類ダウンロード
- コールセンターへの電話問い合わせ
自分に合った方法を選択し、書類の取り寄せを実施しましょう。
» iDeCoはどこがいいの?運用方法・金融機関の選び方
書類の記入

書類を取り寄せたあとは、適切に記入してください。主な記入項目は下記のとおりです。
- 氏名や住所、生年月日などの基本情報
- 加入希望の運用機関と加入者番号
- 掛金の金額と引き落としの口座情報
- 配偶者や扶養家族に関する情報
- 申込者の職業や勤務先情報
- 自筆の署名
提出前に必要書類のコピーを取っておくことで、万が一のトラブル時にも対応できます。
» iDeCo(個人型確定拠出年金)を始めるための必要書類を解説
書類の提出
必要な書類に記入漏れや誤りがないかを確認しましょう。本人確認のため、住民票の写しと本人確認書類のコピーも必要です。基本手数料の振込証明書も忘れずに準備しましょう。必要な書類一式をまとめて金融機関に提出します。必要な書類を提出すると、iDeCoの申請が完了します。
iDeCoのよくある質問

iDeCoに関するよくある質問を下記にまとめました。iDeCoを始める前に、疑問点を解消しておきましょう。
- 60歳以降も働いているときはどうなる?
- iDeCoと他の年金制度は併用できる?
- 投資商品を選ぶときのポイントは?
60歳以降も働いているときはどうなる?
60歳以降も働いている場合は、iDeCoの掛金拠出期間を65歳まで延長できます。掛金拠出の延長だけでなく、iDeCoの受取開始年齢も状況に応じて変更可能です。受給開始年齢は75歳まで延長できるので、働いている間はiDeCoの運用を継続できます。60歳以降も延長することで、長期的な資産形成が可能です。
iDeCoと他の年金制度は併用できる?

iDeCoは公的年金である国民年金や厚生年金と併用できます。iDeCoの積立金は将来の年金受給額に追加されます。iDeCoは確定給付企業年金や企業型DC(確定拠出年金)との併用も可能です。ただし、特定の企業年金とは併用できない場合もあるので、勤務先の年金制度を確認してください。
企業型DCに加入している場合、iDeCoの掛金には制限が生じるので注意が必要です。公務員もiDeCoに加入できるようになることで、幅広い職業の方が利用しやすい制度となりました。併用時の掛金上限は各年金制度により異なるため個別に確認してください。
投資商品を選ぶときのポイントは?
投資商品を選ぶ際は、下記のポイントを意識してください。
- 自分のリスク許容度を把握する
- 投資対象を確認する
- 投資にかかる手数料を把握する
- 過去の運用実績を確認する
- 長期的な視点で運用する
投資をする上で、リスク許容度の把握は欠かせません。自分が受け入れられるリスクの把握により、適切な投資商品を選ぶ際の判断材料となります。リスクをあまり取りたくない方は、債券や定期預金などの安全性の高い商品がおすすめです。
商品の投資対象の確認も重要です。さまざまな投資先に分散投資することで、リスクを分散できます。株式や債券、不動産など、さまざまな資産クラスに投資することでリスクの軽減が可能です。投資商品の手数料の比較も忘れずに実施してください。
手数料は投資のパフォーマンスに大きく影響するため、できる限り低コストの投資商品を選択してください。同じ投資先の投資信託でも手数料が異なる場合があるので、必ず確認しましょう。投資商品の過去の運用実績も、投資のパフォーマンスに関わるため確認が欠かせません。
過去数年の実績やボラティリティを確認すると、商品の将来性の予測に役立ちます。投資は長期的な視点で運用することを意識しましょう。短期的な値動きではなく、長期的に安定したリターンを期待できる商品を選ぶ必要があります。
長期的な視点を持つことで、市場の一時的な変動に対して慌てること無く冷静に対処できます。
» iDeCoの投資信託のラインナップ
まとめ

iDeCoは老後資金を効率的に貯められる可能性のある制度です。所得税や住民税の節税効果もあるので、資金を効率よく運用できます。iDeCoは50〜60代から始めてもさまざまなメリットが得られます。ただし、加入期間や運用期間が短くなるため、注意してください。
iDeCoの手続きには書類の取り寄せや記入、提出が必要です。他の年金制度と併用できる点もおすすめです。投資商品の選び方は投資成績に大きく影響するので、しっかりと検討してください。
iDeCoを適切に活用することで、安心した老後生活を送れます。iDeCoの基礎知識を身に付けて、お得に老後資金の準備を実施してください。