PR
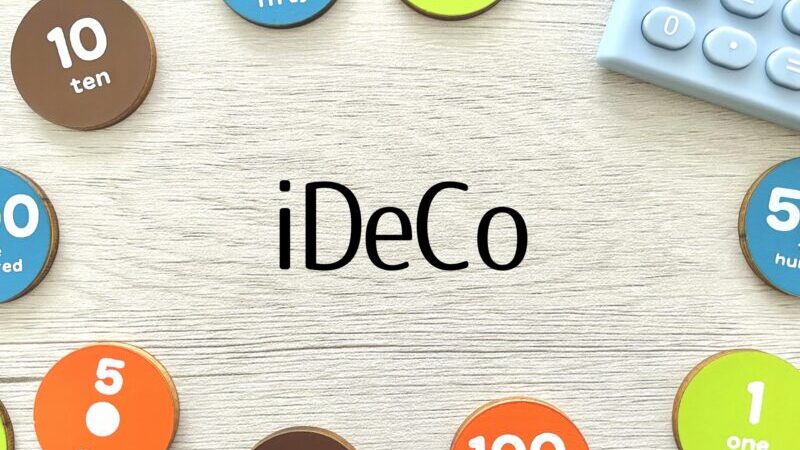
iDeCoの上限額は、資産形成を考える多くの方が気になるポイントです。実はiDeCoの掛金上限は、職業や加入状況によって異なります。この記事では、iDeCoの上限額を職業や加入条件別に詳しく解説します。記事を読むことで、上限額や拠出額の決め方がわかり、iDeCoを最大限に活用することが可能です。
iDeCoで資産形成を始めるには、自分に合った上限額を理解し、無理のない拠出額を設定することが大切です。2024年12月からの上限額変更を踏まえ、節税効果や運用目標に応じて最適な拠出額を設定しましょう。
iDeCo(確定拠出年金)とは投資商品で資産を形成する年金制度

iDeCo(イデコ)とは、個人で掛金を拠出し、運用商品を選んで資産を形成する年金制度です。iDeCoを上手に活用することで、老後の生活資金の準備ができます。自営業者をはじめ、会社員や公務員、専業主婦(夫)など幅広く利用可能です。
年間の掛金の上限額は、職業や年金制度によって異なり、2024年12月からは変更が予定されています。
iDeCoのメリット・デメリット
iDeCoには、節税効果が期待できるメリットがあります。さまざまな控除対象があり、運用益が非課税です。主な控除対象は、iDeCoの掛金や退職所得、公的年金などです。控除以外にも、老後資金を計画的に積み立てでき、資産運用の選択肢を広げられるといったメリットもあります。
大きなメリットがあるiDeCoですが、知らないと損するデメリットもあります。最大のデメリットは、iDeCoは投資商品で元本保証がないため、運用次第で損失リスクがあることです。運用には手数料や口座管理料もかかります。掛金の変更は、年に1回のみ可能です。
原則60歳までは資金を引き出せず、解約時や受け取り時の状況に応じて課税される可能性がある点もデメリットといえます。最適な資産運用をするためにも、iDeCoのメリットとデメリットをしっかりと理解しましょう。
» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説
iDeCoの上限額

iDeCoの上限額は、以下の職業によって異なります。
- 自営業・フリーランス
- 企業年金がない会社員
- 企業型DCのみ加入している会社員
- 企業型DCとDBに加入している会社員
- DBのみ加入している会社員
- 公務員
- 専業主婦
職業によって上限額が異なる理由は、収入や年金制度の違いによって設定されているためです。詳しいiDeCoの上限額は、職業ごとに解説します。
自営業者・フリーランス
自営業やフリーランスのiDeCoの掛金は、上限が月額68,000円、年間816,000円に設定されています。他の職業よりも上限額が高いのが特徴的です。上限額が高く設定されている理由は、企業年金がなく老後資金の積み立て手段が限定的なためです。
掛金は全額所得控除の対象となるので、まとまった金額を積み立てることで所得税や住民税の負担を軽減できます。ライフスタイルに合わせて掛金の調整も可能です。自営業やフリーランスのiDeCoに関する相談は、専門的なアドバイスやサポートを行っている金融機関を利用しましょう。
» 個人事業主にiDeCoはおすすめ?基本知識や始め方を解説
企業年金がない会社員

企業年金がない会社員のiDeCoの掛金は、月額23,000円、年額276,000円が上限です。会社の企業年金を受給できないため、老後資金の自己管理が必要です。企業年金のない会社員にとってiDeCoは、老後のための資産運用として活用できます。
iDeCo以外にも、投資信託や株式、保険商品など資産を運用できる方法があります。老後資金を計画的に積み立てるには、積極的な資産運用も大切です。iDeCoと併用して、NISAなどの投資制度の活用も効果的な資産形成を目指せます。
» iDeCoの投資信託のラインナップ
企業型DCのみ加入している会社員
企業型DCのみ加入している会社員のiDeCoの掛金は、月額2万円、年額24万円が上限です。企業型DCは、確定拠出年金のことです。iDeCoとの併用で、税制優遇を受けながら老後の資産形成を図れます。
iDeCoの加入には一定の手続きが必要です。企業型DCを併用する場合は、拠出額の合計が法定上限を超えないように注意しましょう。企業型DCの月の拠出額が15,000円の場合は、iDeCoの掛金の上限は5,000円です。
投資リスクを抑えてiDeCoとのバランスを保つためには、企業型DCの運用商品の見直しも大切です。 税制優遇を受けるためにも、自分に適した運用商品やサービスを提供している金融機関を選び、安定した資産形成を目指しましょう。
企業型DCとDBに加入している会社員

企業型DCとDBに加入している会社員のiDeCoの掛金は、月額12,000円、年額140,000円が上限です。DCは確定拠出年金、DBは確定給付企業年金のことです。企業型年金制度が整備されているため、個人型のiDeCoの上限額は、低めに設定されています。
上限額が低くても、年金受取額を増やすために企業型年金と併用してiDeCoを補完的に活用するパターンも多いです。2024年12月からは、iDeCoの上限額引き上げの可能性もあるので、状況に応じた掛金の見直しもおすすめです。
DBのみ加入している会社員
DB(確定給付型年金)のみ加入している会社員のiDeCoの掛金は、月額12,000円、年額144,000円が上限です。DBは、DC(確定拠出年金)や他の年金制度と併用できないため、iDeCoの利用で税制優遇を受けながら資産形成できます。
DBには企業からの追加の拠出がないことから、iDeCoを補助的に利用した老後資金の準備もおすすめです。iDeCoの月々の掛金上限額をライフスタイルに合わせて調整することで、計画的な資産運用を目指せます。
» 会社員がiDeCoに入るメリットと年代別の節税効果を解説
公務員

公務員のiDeCoの掛金は、月額12,000円、年額140,000円が上限です。退職金や年金制度が充実しているため、iDeCoの掛金の上限が他の職業よりも低く設定されています。iDeCoを利用しなくても、老後の資金を十分準備できますが、節税効果や資産を効率的に増やす方法として活用可能です。
公務員がiDeCoに加入する場合は、受給できる年金額や退職金額を確認しましょう。受給額によっては、iDeCoのメリットが少ないです。2024年12月に予定されているiDeCoの上限額の変更により、メリットが増える可能性もあります。最新情報を確認し、効果的な資産形成を目指しましょう。
» 公務員がiDeCoで効率的に資産を増やす方法を解説
専業主婦(夫)
専業主婦(夫)のiDeCoの掛金は、月額23,000円、年額276,000円が上限です。iDeCoへの拠出金が控除されるため、節税効果として所得税や住民税の負担を軽減できます。年金だけでは、老後の生活が不安な方にiDeCoの活用が期待できますが、控除対象の所得がないとメリットが少ないです。
iDeCoに加入する際は、口座管理などの手数料や投資商品による運用リスクが伴うことを考慮しましょう。節税効果や老後の資金調達を目指したものの、資産を減らす結果にならないように計画的な運用が大切です。
» 節税メリット大!iDeCoで主婦(夫)が賢く貯蓄する方法
2024年12月からiDeCoの上限額が変わる

2024年12月からiDeCoの掛金上限額の変更が予定されています。上限の増額が見込まれていて、以前よりも多くの資金を積み立てられる可能性が高いです。以下2点について詳しく解説します。
- 変更の背景
- 新しい掛金の拠出上限額
変更の背景
iDeCoの掛金の上限額変更は、高齢化社会が進んだことによって年金財政の圧迫が懸念されていることが背景の1つです。年金財政の圧迫により、現行の制度では限界があり、個人の努力による老後資金の準備も必要とされています。
年金財政の圧迫は、現行のiDeCoの制度にも影響を及ぼしています。現行の掛金の上限額では、十分な老後資金の確保が難しいとされ、制度の見直しが求められていました。個人の資産形成の支援や国際的な年金改革の動向により、iDeCoの掛金の上限額変更など制度の見直しが進められています。
新しい掛金の拠出上限額
2024年12月から変更が予定されているiDeCoの掛金の月額上限は、以下のとおりです。
- 自営業者・フリーランス:90,000円
- 企業年金のない会社員:27,000円
- 企業型DCのみ加入の会社員:27,000円
- 企業型DCとDBに加入の会社員:14,000円
- DBのみ加入の会社員:変更なし(12,000円)
- 公務員:14,000円
- 専業主婦(夫):27,000円
DBのみ会社員の上限額の変更はありませんが、職業によって月額2,000〜22,000円の増額が予定されています。iDeCoの掛金の上限が増額されることにより、運用次第で現行よりも多くの老後資金の調達が見込めます。
» iDeCoの掛金の上限や、金額の決め方のポイントを解説!
iDeCoの拠出額を決めるときのポイント

iDeCoの拠出額を決めるときの主なポイントは、以下のとおりです。
- 目標金額
- 運用期間
- 家計
ポイントを押さえれば、効果的な節税や老後の資産形成が期待できます。将来のライフイベントを見据え、税制優遇を最大限活用することも大切です。資産分散を考慮し、リスクの許容範囲を見極めると運用の安全性が高まります。iDeCoの拠出額を適切に決められるようにポイントごとに詳しく解説します。
目標金額
目標金額は、iDeCoの拠出額を決める重要なポイントの1つです。主に以下の目的から目標金額を設定すると、拠出額を決めやすいです。
- 年金受給額の補填
- 老後の生活資金
- 住宅ローン完済後の生活費
- 子供の教育資金
- 自己投資資金
- 健康維持や医療費対策
- 娯楽資金
- 予備費
目的に応じて、どのくらいの資金が必要なのか見積もると、目標金額を設定できます。現在の生活費をベースに将来の予想支出を考慮し、iDeCoの拠出額を決めることも大切です。安心して老後を過ごせるように、目標金額とのバランスを考えて、計画的にiDeCoの拠出額を決めましょう。
運用期間

iDeCoの拠出額は、運用期間を考慮して決めることも大切です。iDeCoは長期運用に適していて、最低加入期間は加入時の年齢から60歳までです。原則60歳までは、運用資金の引き出しができないため、加入時の年齢が若いほど運用期間が長くなります。
運用資金の受け取りは60歳から開始でき、最大75歳まで延長可能です。iDeCoの運用期間が長いほど、投資リスクを分散できます。老後の資産を増やすためにも、なるべく長期間のiDeCoの運用がおすすめです。
家計
iDeCoの拠出額を決めるときには、家計の状況を考えて毎月の収入と支出を把握しましょう。無駄な出費を抑えることでiDeCoの拠出額を増やせます。家計の中でも家賃や通信費、保険料などの固定費は見直しにより削減可能です。
家族で協力し合って家計を管理すれば効率的に見直せます。クレジットカードを持っている場合は、無駄な利息がないか利用状況を確認しましょう。食費や娯楽費などの変動費は、無駄遣いを避けると家計の負担を減らせます。
家計簿をつけて支出を見直し、家計を管理することも大切です。利用していないサブスクリプションがあれば、解約することでiDeCoの拠出額に充てられます。緊急の出費を考えて予備資金を確保しつつ、収入を増やせるように副業やスキルアップを検討するのもおすすめです。
iDeCoのよくある質問
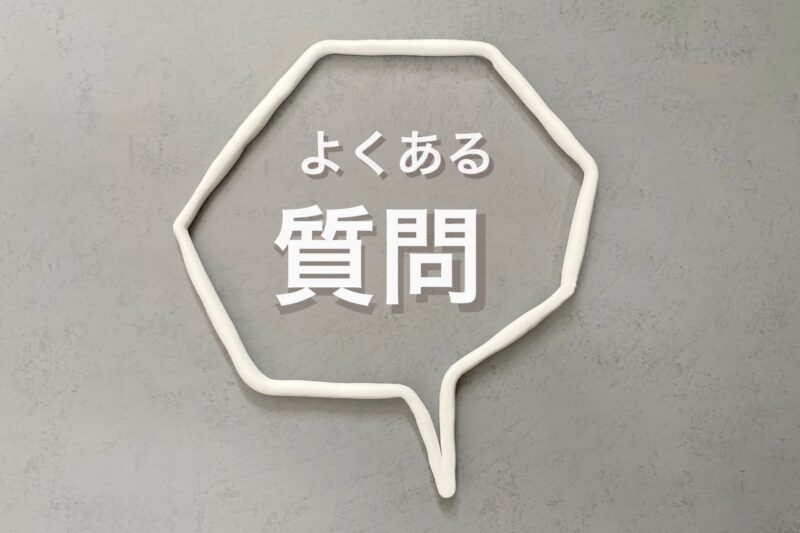
iDeCoに関するよくある質問を紹介します。拠出額の上限の関連情報として、参考にしてください。
- iDeCoとNISAの違いは?
- iDeCoはどのように受け取れる?
- 60歳でもiDeCoは加入するべき?
iDeCoとNISAの違いは?
iDeCoとNISAは、主に投資目的や引き出し可能時期、手数料などが違います。iDeCoとNISAの違いを以下にまとめます。
| 比較ポイント | iDeCo | NISA |
| 投資目的 | 老後の年金受給 | 資産を増やすこと |
| 引き出し可能時期 | 原則60歳以降 | いつでも |
| 口座管理の手数料 | 有料 | 無料 |
| 節税の優遇 | 掛金全額所得控除 | 投資収益非課税 |
| 年間の投資可能額 | 職業によって変動 | つみたて投資枠:最大120万円 成長投資枠:最大240万円 |
iDeCoはどのように受け取れる?

iDeCoは、退職所得扱いの一時金と雑所得扱いの年金を選んで受け取り可能です。一時金と年金の併用もできます。一時金は1度にまとまった資金を、年金は毎年一定額を受給可能です。大きな出費を控えている場合は一時金を、生活費として安定的な受給を希望する場合は年金がおすすめです。
一時金と年金の併用は、リスクを分散して受け取れます。受け取りを開始できる年齢は、受給方法に関わらず原則60〜75歳と決められています。安心して老後を送れるように、退職後のライフスタイルや必要な金額に応じて、iDeCoの受け取り方法を選びましょう。
60歳でもiDeCoは加入するべき?
60歳からのiDeCoの加入は、元本確保型のプランがおすすめです。60歳からでは、長期的な運用が難しいため、リスクの少ない商品を選ぶと安心して加入できます。元本が保証されていてリスクの少ない商品は、定期預金や保険商品などです。
60歳からiDeCoに加入する場合は、最低5年間の運用期間が必要です。掛金が全額所得控除対象であり、受け取る際も退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。iDeCoは、老後の資金確保しながら節税対策ができるため、60歳からの加入でもメリットがあります。
» iDeCoで選べる定期預金の特長やメリット・デメリットを解説
まとめ

iDeCoの上限額は、職業によって月額12,000〜68,000円です。2024年12月からは、社会情勢の影響で上限額の増額が予定されています。長期的な資産形成を目指せて、税制が優遇されますが、投資リスクや60歳までは引き出しできないなどのデメリットもあります。
iDeCoの拠出額を決めるには、目標金額や運用期間、家計などの考慮が大切です。安全な資産運用を目指すためにも、現在の職業の拠出上限額を把握し、最適なプランを選びましょう。iDeCoとNISAの違いや受け取り方法など、上限額以外の情報を把握しておくと、資産形成の理解を深められます。